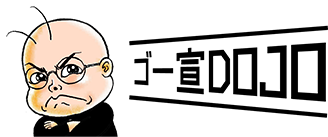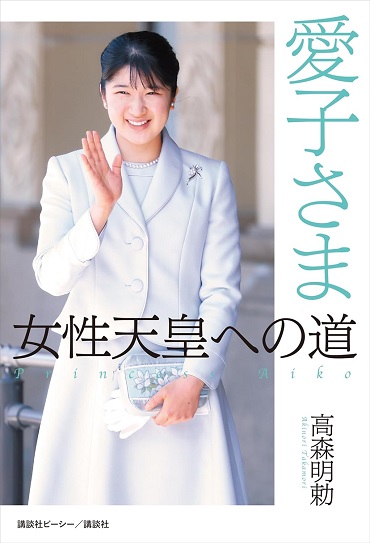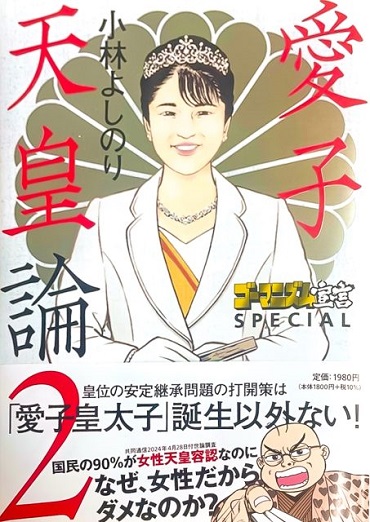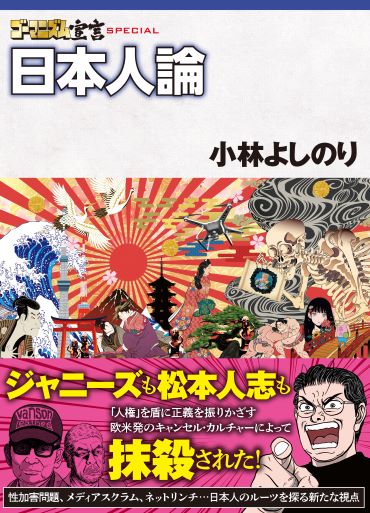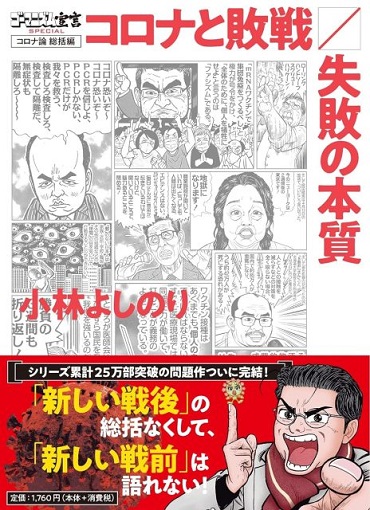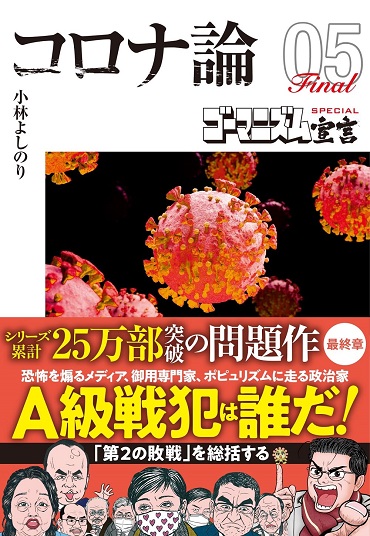~光る君へ~
愛子さま立太子への祈念と読む「源氏物語」
第36回第三十六帖<柏木(かしわぎ)>byまいこ
「光る君へ」第41回は、「そなたと明子の間の子・顕信を蔵人頭(天皇の傍に仕える蔵人所のトップ)にしてやろう」という三条天皇の打診を道長が断っていました。顕信は絶望して出家してしまい、「あなたが顕信を殺したのよ」と道長に詰め寄りながら明子が放つ言葉は、髪を下ろした際に「私は生きながら死んだ身である」といった定子の言葉と同じく、「源氏物語」を現代語訳した瀬戸内寂聴さんの「出家とは、生きながら死ぬこと」が反映されているように思います。
今回は、生きながら死ぬことを選ぶありさまをみてみましょう。
第三十六帖 <柏木 かしわぎ(柏の木は樹木を守る葉守の神が宿るとされたことから皇居守衛の任に当たる衛門のたとえ 柏木の身分は衛門督 落葉の宮の歌より)>
柏木は寝ついたまま快方に向かわず、父の致仕の大臣も母も嘆いています。何ごとも人より一際、秀でたいと公私にわたって自負してきた柏木でしたが、その思いは叶わず、誰も千年の寿命が続く松のごとく、この世では、いつまでも生き残れないのなら、少しは偲んでもらえる間に儚くなり、かりそめでも情けをかけてくれる人がいるのを一心に燃えた恋の証しにしようと、女三宮に文を書きました。
今はとて燃えむ煙もむすぼほれ 絶えぬ思ひのなほや残らむ 柏木
今はもう最期と燃える荼毘の煙もくすぶって空に昇れず 私の絶えぬ思いは なおもこの世に残るでしょう
小侍従に強いられて女三宮はしぶしぶと返事を書きます。
立ちそひて消えやしなまし憂きことを 思ひ乱るる煙くらべに 女三宮
立ち上る煙と共に消えてしまいたい くすぶる辛い悩みを思い比べながら
「この煙くらべの歌こそが、この思い出となるだろう。儚いものだ」と柏木は泣くのでした。
女三宮は、この日の夕暮れの頃、産気づき、苦しみながらも、朝日がさし昇る頃に男の子・薫を産みました。光る君は「男の子で柏木と瓜二つの顔つきで生まれていたら不都合だ。女の子なら何となく取り紛れて、大勢の人が見るわけではないから心配はないのに」と悩む一方で「こんなにやりきれない疑いの付きまとう子ならば、手のかからない男の子で良かったのかもしれない。それにしても不思議だ。この子は私が生涯を通して恐ろしいと思ってきた不義の報いなのだろう。この世でこうして思いがけない報いに遭ったならば、後の世の罪も少しは軽くなるだろう」と思います。
世間の人々は事情を知らないので、高貴な身分の女性から、しかも晩年になって生まれた男の子への光る君の愛情は深いだろうと噂しています。産屋(うぶや 出産祝い)の儀式は盛大で、六条院の女性は祝いの品々を競い合い、帝からも公式のお祝いがあります。致仕の大臣も格別にお祝いするつもりでしたが、この頃は息子の柏木の病に気をとられて何も考えられず、一通りの挨拶があっただけでした。
女三宮は、か細く弱々しい体で初めて出産したことが恐ろしく、薬湯なども摂らないまま、不義の子を産んだ身の上の苦しさを感じて「このついでに死んでしまいたいと」思います。光る君は生まれた子を特に見ようともせず、夜も泊まらずに昼に少し顔を出すだけなので、女三宮は「お産で死ぬのは罪が重いとか言われますので、尼になった功徳で生きながらえるか試み、また亡くなるとしても、罪の消えることもあるかと思います」と、いつもより遥かに大人びた様子で伝えました。
光る君は「縁起でもないこと」などと言いながら心の中では「尼になられた上でお世話するのが情けというものもかもしれない。我ながら思い直せそうもなく、女三宮を疎かにしているなどと朱雀院が聞かれたら、怠慢と思われるだろうし、病にかこつけて出家させてあげた方がいいのだろうか」と思いつつ薬湯をすすめるのでした。
朱雀院は、出産後、物も食べられずに日が経っている女三宮が「もう父君にお会いできないままなのでしょうか」と泣いていると聞いて堪えがたくなり、夜に紛れて西山の寺から六条院にやってきました。光る君が恐縮して挨拶すると「俗世のことは顧みないと決心したのですが、やはり惑いの覚め難いのは子を思う親の心の闇でした」などと朱雀院は応えます。御帳台(みちょうだい 寝所)の前に通された朱雀院に、女三宮は「生きていられそうもありませんので、お越しいただいたついでに尼にして下さい」と頼みました。
朱雀院は、光る君ならば先々まで安心と思って女三宮を降嫁させたのに、期待していたほどの待遇をされていないと聞いても忍んできたので「この折に出家すれば外聞も悪くないかもしれない。桐壺院の遺産の邸を修繕して女三宮を住まわせよう。光る君も見捨てることはあるまい」などと思って「それでは、受戒をして、仏縁を結びましょう」と伝えます。光る君が御簾の内に入って出家を止めても、女三宮は頭を振るのでした。
六条院で病の祈祷をしていた有徳の僧に女三宮の髪を下ろさせて、朱雀院は西山の寺に帰ります。光る君が堪え難く思っていると、物の怪が現れて「それ御覧。紫の上を取り返したと思われて妬ましかったので、この方の辺りで、さり気なく取り憑いていたのよ。さあ帰ることにしましょう」と声を上げて笑います。光る君は、あの物の怪がまだ離れずに女三宮を尼にしてしまったことを悔やみ、祈祷を続けさせます。
柏木は女三宮の出産と出家のことを聞き、ますます容態が悪くなり、回復の見込みも無くなりました。妻の落葉の宮が気の毒なので、一条の邸に行きたいと願いますが、両親が許さないので、柏木は誰彼となく落葉の宮のことを頼みます。帝は、権大納言に昇進させれば、今一度、参内できるのではと期待しましたが、柏木は病で苦しいなか、御礼の言上を述べるだけに留まりました。夕霧も昇進の祝いに真っ先に駆けつけますが、柏木は息も絶え絶えで「光る君と行き違いがあったので、何かの折に取りなして下さい。亡き後にでもお咎めが許されたら、あなたの御恩を有難く思います」などと言いつつ、いよいよ苦しそうです。
「どうして心の鬼、罪悪感に苛まれることになったのでしょう」などと夕霧は尋ねますが「このことは、どうか心に収めて漏らさないで下さい。また一条の邸にいる落葉の宮を何かにつけて訪ねてやってください」と応えた柏木は気力が尽きて「もうお帰りください」と手真似で伝えます。加持の僧や、柏木の母や父の致治の大臣なども集まってきたので、夕霧は泣く泣く帰りました。
妹の弘徽殿女御も雲居の雁も嘆き、玉鬘も祈祷をさせましたが、恋の病には効き目がなく、落葉の宮にも会えないまま、柏木は亡くなります。落葉の宮はふさぎ込み、落葉の宮の母・御息所も降嫁して夫に先立たれた娘の身の上を悲しんでいます。まして柏木の両親は「自分たちこそ先立ちたかった」と亡き息子を恋焦がれています。
柏木の恋心が厭わしかった女三宮も、亡くなったと聞くと憐れに思うのでした。
三月(新暦で四月 旧暦は新暦の約一ヶ月前)になり、生まれて五十日の祝いを迎えた薫は、色白で可愛らしく、発育も良くて何か口をきこうと声を上げています。光る君が抱き取ってみると、薫は夕霧の幼い時と比べても似ておらず、気品と愛嬌があり、目元が艶やかで、やはり柏木に似ています。「柏木の両親がせめて子供でも残していてくれたらと泣いているそうだが、逢わせるわけにはいかない。人知れず形見を残して、自ら身を滅ぼしてしまうとは」と憎む心も思い直して泣いてしまう光る君。「こんなに可愛い子を見捨てて出家されるほどのことがあったでしょうか」と光る君が言うと、尼となった女三宮は顔を赤らめてひれ伏してしまうのでした。
夕霧は柏木がやはり女三宮のことを言いたかったのだろうかと考えて、光る君にも話して顔色を窺ってみたいと思っています。夕霧も落葉の宮のことを頼まれていたので一条の邸を訪ねてみると「柏木さまがいらしたかと思ってしまいましたわ」と泣く女房もあり、落葉の宮の母・御息所と亡き柏木についてしみじみと話すことができました。四十九日の法要の際にも一条の邸を訪ねた夕霧は、気分の優れない御息所の代わりに小少将という女房と話していた際に、ふと庭の木立に柏木と楓が枝をさし交わしているのを見て歌を詠みました。
ことならば馴らしの枝にならさなむ 葉守の神のゆるしありきと 夕霧
柏木と楓が枝をさし交わすように馴れ親しんだ亡き人と私 同じことならば あなたと親しくなりたいのです 樹木を守る葉守の神・亡き人のゆるしを得たことにして
落葉の宮は小少将に取り次がせて返歌します。
柏木に葉守の神はまさずとも 人ならすべき宿の梢か 落葉の宮 (柏木の呼び名はこの歌から)
柏木に宿るという葉守の神・亡き夫はいなくとも ここは別の人を馴れ馴れしく近づけて良い場所でしょうか
「今は私を亡き人と同じように考えて、よそよそしくなさらないで下さい」などと、ことさらに言い寄る様子はないのですが、何となく思いが外に現れてしまう夕霧なのでした。
***
「源氏物語」におけるNTR、ネトラレ、「寝取られ問題」。①「コキュ(カッコウ 托卵することから)妻に間男されて気づかない夫」、②「コルネット(頭巾をかぶった)妻に間男されても許す夫」、③「コルナール(角をはやした)妻に間男されて怒り騒ぐ夫」のうち、桐壺帝と、脚本担当の大石静さんによれば「理想の男」・宣孝は②と思われますが、光る君は残念ながら③であることが明らかになり、とうとう柏木は亡くなってしまいました。
2024年の秋ドラマ「わたしの宝物」は、夫(田中圭さん)に顧みられない妻(主演・松本若菜さん)が、夫以外の男性(Snow Manの深澤辰哉さん)との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵(たくらん)」がテーマでした。「若菜(偶然にも主演女優さんの名と同じ)」の帖から始まった光る君、女三宮、柏木の関係性は、古今、いつでも起こり得るものなのでしょう。
「光る君へ」第32回、安陪清明は臨終の際、道長に「ようやく光を手に入れられましたな。これで中宮様も盤石でございます。いずれあなた様の家からは、帝も、皇后も、関白も出られましょう。お父上が成し得なかったことを、あなた様は成し遂げられます」「ただ一つ、光が強くなれば闇も濃くなります。そのことだけは、お忘れなく」「呪詛も祈祷も、人の心の有り様なのでございますよ。私が何もせずとも、人の心は勝手に震えるのでございます」と語っていました。
柏木が、心の鬼、罪悪感に苛まれて、この世を去ってしまったのは、「人の心が勝手に震え」た結果ということになりそうですが、何度も間男の役割を演じ、あまつさえ父である帝の后と不義の子をなしている光る君の心の鬼は、どうなっているのでしょうか。
心の鬼という言葉に関連して、『紫式部集』に、紫式部の物の怪観が現れているという歌があります。
物の怪が憑いて醜い姿になった女・後妻の後ろで、小法師(若い下級法師)が死んで鬼・物の怪となった先妻を縛り、夫が経を読んで物の怪が退散するように調伏している絵を見て詠んだ歌
亡き人にかごと(託言 言いがかり)はかけてわづらふも をのが心の鬼にやはある 「紫式部集 四十四番」
亡き人・もののけに かこつけて 難儀しているのは 己が心の鬼に責められているのではないだろうか
紫式部が描く物の怪に、心の鬼(良心の呵責 疑心暗鬼 罪悪感)という面があるとすれば、光る君の前に何度も現れる六条御息所の物の怪も、光る君の心模様の写し、心の鬼が現れたものと言えるかもしれません。
【バックナンバー】
第1回 第一帖<桐壺 きりつぼ>
第2回 第二帖<帚木 ははきぎ>
第3回 第三帖<空蝉 うつせみ>
第4回 第四帖<夕顔 ゆうがお>
第5回 第五帖<若紫 わかむらさき>
第6回 第六帖<末摘花 すえつむはな>
第7回 第七帖<紅葉賀 もみじのが>
第8回 第八帖<花宴 はなのえん>
第9回 第九帖<葵 あおい>
第10回 第十帖 < 賢木 さかき >
第11回 第十一帖<花散里 はなちるさと>
第12回 第十二帖<須磨 すま>
第13回 第十三帖<明石 あかし>
第14回 第十四帖<澪標 みおつくし>
第15回 第十五帖<蓬生・よもぎう>
第16回 第十六帖<関屋 せきや>
第17回 第十七帖<絵合 えあわせ>
第18回 第十八帖<松風 まつかぜ>
第19回 第十九帖<薄雲 うすぐも>
第20回 第二十帖<朝顔 あさがお>
第21回 第二十一帖<乙女 おとめ>
第22回 第二十二帖<玉鬘 たまかずら>
第23回 第二十三帖<初音 はつね>
第24回 第二十四帖<胡蝶 こちょう>
第25回 第二十五帖<蛍 ほたる>
第26回 第二十六帖<常夏 とこなつ>
第27回 第二十七帖<篝火 かがりび>
第28回 第二十八帖 <野分 のわき>
第29回 第二十九帖 <行幸 みゆき>
第30回 第三十帖 <藤袴 ふじばかま>
第31回 第三十一帖<真木柱(まきばしら)
第32回 第三十二帖<梅枝(うめがえ)>
第33回 第三十三帖<藤裏葉(ふじのうらば)>
第34回 第三十四帖<若菜上(わかなのじょう)>
第35回 第三十五帖<若菜下(わかなのげ)>
柏木も儚く死んでしまいました。
女三宮に恋焦がれて、強引に成就させたような形になったものの、結局はその恋の炎で自らを焼き尽くしてしまったわけで、何とも切ない話です。
女三宮にしても、柏木の恋は本当は迷惑だったのだろうし、それで不義の子まで産んでしまい、若い身ながらもはや出家しかなくなってしまったというのがなんとも哀しい。
で、そうなってしまったのも、結局は、光る君のせいじゃないですか!?
一体この先、どうなってしまうのでしょう?