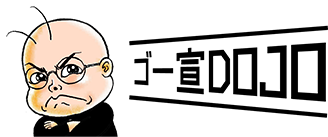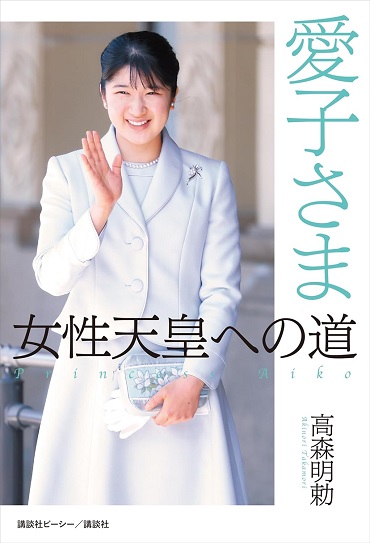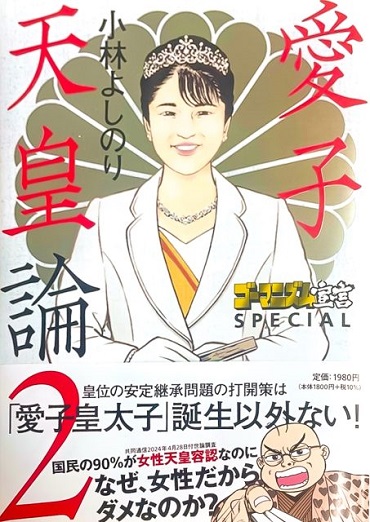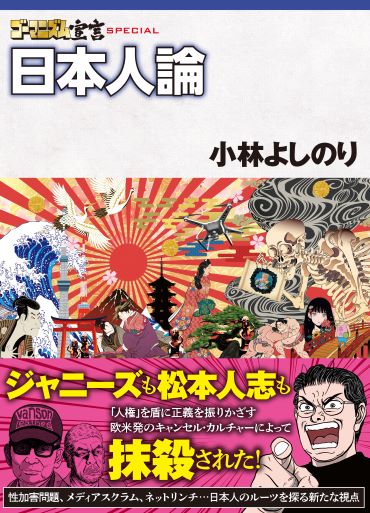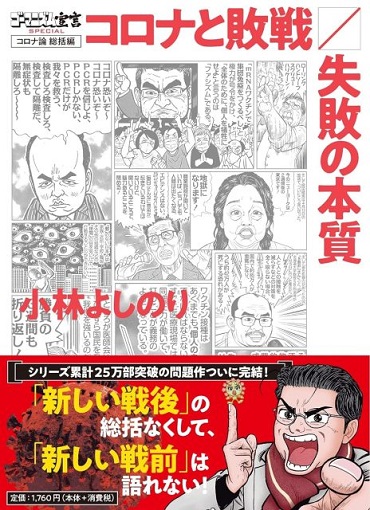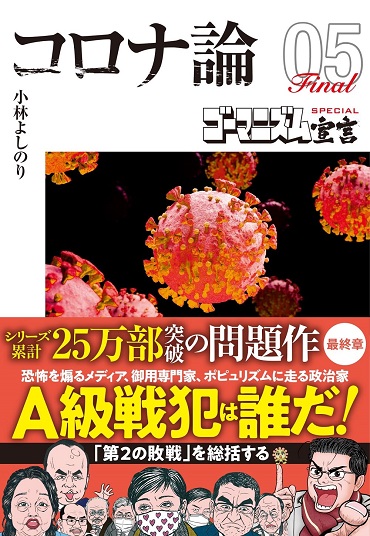~光る君へ~
愛子さま立太子への祈念と読む「源氏物語」
第35回 第三十五帖<若菜下(わかなのげ)>byまいこ
「光る君へ」第40回、彰子を慕う敦康親王が「藤壺は光る君のことを愛おしんでいたと思うことにします」と言うと「たとえ藤壺の思いを得たとしても光る君は幸せにはなれなかったと思いますが。不実の罪は必ず己に返ってきますゆえ」と道長は応えていました。その道長に、和泉式部は「罪のない恋なぞ、つまりませんわ」赤染衛門は「人は道険しき恋にこそ燃えるのでございます」と反駁していたのは真に艶なる場面でした。
今回は、道険しき恋がどうなるかをみてみましょう。
第三十五帖 <若菜下 わかなのげ(「若菜」の帖は最も長編で上下に分れる)>
柏木は女三宮への恋が身の程知らずと悩みつつ、あの唐猫が欲しくて狂おしくなり、女三宮の兄・東宮を通じて手に入れると、夜も添い寝して可愛がります。「ねうねう」と鳴く声に「寝よう寝ようなんて気が早いね」と猫を懐に入れ物思いする柏木を、女房たちも不審に思っています。
蛍兵部卿宮は亡き愛妻と似た女性を望んで髭黒の大将の元の正妻が産んだ娘・真木柱と再婚しました。ところが兵部卿宮が真木柱に通う様子が物憂げなので、祖父の式部卿宮は嘆き、髭黒の大将も面白くありません。結婚して二年経ち、淡白な関係に馴れた兵部卿宮と真木柱は、こういう夫婦仲として暮しています。
年月が重なって冷泉帝は譲位して冷泉院となり、太政大臣は辞職して致仕の大臣(ちじのおとど 引退した大臣)と呼ばれるようになりました。新しい帝の伯父・髭黒の大将は右大臣に、夕霧は大納言に昇進。明石の女御の生んだ皇子は東宮となり、さらに次々、御子が生まれていますが、光る君は藤壺との不義の子・冷泉院に皇子が生まれず、帝位が継がれないことを寂しく思います。
明石の女御の皇子の立太子を機に、明石の入道が住吉の神に立てた願ほどきの参詣をすることになり、光る君は明石の尼君も連れて行きます。「明石の尼君」は幸運の象徴として、あの近江の君も双六のお呪いに「明石の尼君!明石の尼君!」と唱えるほど持て囃されるのでした。
帝は父の朱雀院から依頼されて女三宮を二品(にほん 親王・内親王の位)の高い位にしました。朱雀院が女三宮に会いたがっているので、光る君は朱雀院の五十の賀(五十歳の祝い)をしようと考えます。朱雀院からは「女三宮の琴を聞いてみたい」と要望があったので、光る君は熱心に教え始めました。
正月の二十日過ぎ(新暦で二月下旬 旧暦は新暦の約一ヶ月前)、光る君は六条院の女性たちに合奏させる女楽(おんながく)の宴を設けました。夕霧も列席して、琴の弦を張って調律し、軽く一曲奏でます。明石の君の琵琶は名人の域、紫の上の和琴は斬新で華やか、明石の女御の箏の琴は可憐で優雅。女三宮の琴は、習っている最中なので、たどたどしくはなく、他の楽器とよく響き合いました。
夜になり、光る君は紫の上の素晴らしい演奏を労います。今年は女の厄年の三十七歳なので用心するように光る君が諭すと、紫の上は出家を願い出ました。光る君は「私の格別な愛の深さを最後まで見届けて下さい」と取り合わず、関係した女性たちのことを話し始めます。
「夕霧の亡き母・葵上は欠点はないけれど、真面目で賢すぎて共に暮らすには気を遣う人でした。六条御息所は情愛の深い方でしたが、会うのに気が重くなるような気難しさがありました。秋好中宮のお世話をしているので、あの世で私を見直してくれるでしょう。明石の君は芯の強い、優れた人ですね」翌日の夕方、「女三宮へも上手に演奏できた祝いをお伝えしましょう」といって出かけた光る君は、まだ一生懸命に練習を続けていた女三宮の琴を押しやって、寝所に入りました。
その明け方、紫の上は胸が苦しくなり発熱します。光る君が懸命に介抱し、祈祷させても治らず、二月になっても容態が変わらないので、場所を変えた方が良いと紫の上は慣れ親しんだ二条院に移されました。紫の上は出家を願いますが、光る君は「私を見捨てるのですか」と言うばかり。光る君は女三宮には全く通わなくなり、六条院は火が消えたような有り様です。
中納言に昇進した柏木は降嫁から七年経っても女三宮への想いが募る一方で、代わりに姉の女二宮と結婚します。身分の低い更衣を母に持つ女二宮を軽んじた柏木は、光る君の居ぬ間に物越しにでも女三宮に恋心を伝えたいと迫るので、小侍従は断りかねてしまいました。
四月十日過ぎ、賀茂の祭を翌日に控えて人が少ない折に、小侍従は柏木を女三宮の御座所の端に座らせました。眠っていた女三宮は、人の気配を光る君と思いますが、抱き上げられ御帳台に下ろされた際に見上げると全く違う男性で、気が動転して汗もしとどに。連綿と語る言葉で柏木と分かっても恐くて何も答えられません。恋心を伝えるだけのつもりだった柏木は、女三宮の可憐さに惑乱して…。
ふと寝入ってしまった夢に、あの唐猫を見て驚く柏木。うつつとは思えぬ出来事に茫然としている女三宮。「前世からの縁と諦めて下さい」と、柏木は唐猫が御簾を引き開けた時のことを話しますが、女三宮は幼子のように泣くばかり。猫の夢は妊娠の印とされていて、その通りにならないとしても、柏木は夢の有り様を恋しく思います。
念願が叶っても、かえって恋心が募り自室に閉じ籠る柏木。事情を知らぬまま、柏木に軽んじられて憂える女二宮。「同じことなら女三宮を妻にしたかったのに」と柏木は手すさびに歌を書きました。
もろかずら落葉を何にひろひけむ 名はむつましきかざしなれども 柏木
何故、落葉のようなつまらぬ方を戴いたのだろう 同じ朱雀院の皇女で仲睦まじい姉妹ではあるけれど
*もろかずら…諸葛は賀茂の祭の桂の枝に葵の花を絡ませた挿頭・かざし(髪飾り)
(これより女二宮を落葉の宮と呼びます)
何が起きたか知らぬ光る君は、稀にしか足を運ばなくなった六条院に居た際に、使者から「紫の上の息が絶えてしまいました」と告げられます。慌てて二条院に戻ると、人々は泣き喚き、加持祈祷の僧たちも帰ろうとしていました。「物の怪の仕業かもしれない」と光る君がさらに祈祷をさせてみると、女の物の怪が童女に憑いて紫の上は生き返ります。
物の怪は六条御息所のようで「私にだけ思い当たることを言ってみよ」と光る君が伝えると、童女は泣きながら歌を詠みました。
わが身こそあらぬさまなれそれながら そらおぼれする君は君なり 六条御息所
わが身は浅ましい姿になりましたけれど 空とぼけているあなたは昔のままのあなた
「秋好中宮のことは有り難いと天翔けながら見ていても、あなたを恨んだ執念だけがこの世に残っているのです。しかも寝物語に私を気難しいなどと言われたのが恨めしく、紫の上を憎んではいませんが、あなたは神仏の加護が強くて近づけませんでした。どうか私の罪の軽くなる祈祷をお願いします。そして中宮には争ったり嫉妬したりしないようお伝えください」
光る君は更に祈祷をさせ、出家を切に望む紫の上の頭頂の髪を少し切り、五戒(ごかい 殺生・盗み・邪淫・妄語・飲酒を慎む)を受けさせます。六月になって、時おり紫の上が頭を上げられるようになっても、光る君は心配で六条院へは滅多に足を運べません。
女三宮は悪阻で苦しんでいます。病気と聞いて六条院を訪れた光る君は、女房から懐妊と告げられ「今頃になって珍しい」と苦しむ様子を可哀想に思います。
光る君が六条院にいると聞き、嫉妬した柏木は小侍従に文を届けました。女三宮は小侍従から見せられた文を茵(しとね 寝具)の下に隠しますが、光る君は薄緑の薄い紙の端が見えているのを引き出して、柏木からと悟ります。「懐妊はこの結果だろう。これからも女三宮の世話をしなくてはならないのか」「柏木風情に女三宮が心を移すとは」などと悩む光る君は、亡き父・桐壺院が実は藤壷との密通を知っていたのではと思い至るのでした。
小侍従から事の次第を知らされた柏木は驚き、宮中にも参内しなくなりました。女三宮の軽率さを強いて思い、恋の熱を冷まそうとしますが、やはり諦められません。
光る君は女三宮の密通で隠れた恋が嫌になっていたところ、朧月夜は遂に出家を遂げてしまいました。「日々の回向の時は私のことを、まず一番に祈って下さるでしょうね」と伝えた光る君の文に「回向は一切衆生(いっさいしゅじょう 生きとし生けるもの)のため。その中にあなたが入っていないということはありませんわ」と返す朧月夜。最後の朧月夜の文を紫の上に見せて、冷淡さを嘆く光る君。朝顔の君も出家してしまい、紫の上は羨ましく思います。
紫の上の病気で延期されていた朱雀院の五十の賀は十二月十日過ぎとして、試楽(しがく 舞楽の予行練習)が六条院で行われることになりました。再三に渡って光る君に誘われたので、柏木は六条院に赴きますが、身の置き所がありません。
日暮れになって舞楽の感興が高まり、老いた上達部たちは涙を流して感動しています。「老いると酔い泣きが止まらないものでね、柏木が私を見て笑っているけれど、若さだって一時のもの。老いは誰にでもやってくるのですよ」と言いながら、柏木に酒を強いる光る君。柏木は耐え難くなって帰宅し、そのまま寝ついてしまいます。
柏木は落葉の宮のいる一条の邸から離れて、父母の邸で養生することになりました。光る君は見舞いの文を届け、夕霧は仲の良い友人が心配でなりません。
***
40歳で女三宮を迎えた光る君は47歳になり、柏木に間男されて、ようやく父・桐壺院が密通の罪に気づいていたのではないかと悟りました。桐壺院は、藤壺が産んだ御子の誕生を喜び、光る君が須磨に隠遁した際は、夢枕に立ち「これは、ほんの少しのことの報いなのだ」と寛大な発言をしています。
それなのに、光る君…放置していた女三宮を奪った柏木を追い詰めてしまうとは。残念ながら「寝取られ問題」①「コキュ 妻に間男されて気づかない夫」、②「コルネット 間男されても許す夫」、③「コルナール 間男されて怒り騒ぐ夫」のうち、光る君は③と言えそうです。
桐壺院に比べて余りにも狭量な有り様は、紫の上を出家させないところにも表れており、一足早く出家できた朧月夜からは「あなたなんてワンオブゼム(one of them)よ」と冷たくされる始末。モテる人が間男された時、いかに振る舞うべきなのか。紫式部は光る君をシビアに読者の反面教師にしているようです。
さて、「べらぼう」第4回、蔦重が東奔西走し制作した「雛形若菜初模様(ひながたわかなのはつもよう」、雛形は見本帳、若菜初模様は正月に初めて着る衣の柄とのことで、玉鬘が光る君の長寿を祝って新年に贈り、帖名となった若菜も髣髴とします。
磯田湖龍斎(鉄拳さん)の描いた遊女の絵に、猫が花瓶を倒すハプニングも女三宮の唐猫のようで、絵を巧みに描き直した唐丸(渡邉斗翔さん)を「始めは春信そっくりの絵を描かせて今春信」で売り出したいと願う蔦重が言及した美人絵で著名な鈴木春信(1725年?-1770)には、若菜を思わせる作品があり、ボストン美術館に所蔵されています。
愛子さまが初の単独公務「夢みる光源氏」展で言及された『湖月抄』などの注釈書や歌舞伎の題材などで、江戸時代に「源氏物語」は流布していたようで、女性と長い綱のついた猫を「あ、若菜」と見立てた人々は、不義密通に繋がる場面を大らかに楽しんでいたのでしょう。
インド版新作アニメでフレンドリッチの輪が広まった際にも、1円玉を「あ、おぼっちゃまくん」と見立てる人々が世界中で爆発的に増える楽しい未来になりそうですね。
【バックナンバー】
第1回 第一帖<桐壺 きりつぼ>
第2回 第二帖<帚木 ははきぎ>
第3回 第三帖<空蝉 うつせみ>
第4回 第四帖<夕顔 ゆうがお>
第5回 第五帖<若紫 わかむらさき>
第6回 第六帖<末摘花 すえつむはな>
第7回 第七帖<紅葉賀 もみじのが>
第8回 第八帖<花宴 はなのえん>
第9回 第九帖<葵 あおい>
第10回 第十帖 < 賢木 さかき >
第11回 第十一帖<花散里 はなちるさと>
第12回 第十二帖<須磨 すま>
第13回 第十三帖<明石 あかし>
第14回 第十四帖<澪標 みおつくし>
第15回 第十五帖<蓬生・よもぎう>
第16回 第十六帖<関屋 せきや>
第17回 第十七帖<絵合 えあわせ>
第18回 第十八帖<松風 まつかぜ>
第19回 第十九帖<薄雲 うすぐも>
第20回 第二十帖<朝顔 あさがお>
第21回 第二十一帖<乙女 おとめ>
第22回 第二十二帖<玉鬘 たまかずら>
第23回 第二十三帖<初音 はつね>
第24回 第二十四帖<胡蝶 こちょう>
第25回 第二十五帖<蛍 ほたる>
第26回 第二十六帖<常夏 とこなつ>
第27回 第二十七帖<篝火 かがりび>
第28回 第二十八帖 <野分 のわき>
第29回 第二十九帖 <行幸 みゆき>
第30回 第三十帖 <藤袴 ふじばかま>
第31回 第三十一帖<真木柱(まきばしら)
第32回 第三十二帖<梅枝(うめがえ)>
第33回 第三十三帖<藤裏葉(ふじのうらば)>
第34回 第三十四帖<若菜上(わかなのじょう)>
それまで何をやっても許され、愛されていた光る君。
これはこういう物語であり、これはこういうキャラなのだから、こうして進んでいくものだろうと思っていたら、年を経て、かろうじて保たれていた均衡が崩れると共に、それまで見逃されてきたその人物の狭量さが露わになっていくところを冷徹に描いていくとは驚きです。紫式部、おそるべしです!
しかし光源氏はこのまま、落日の様相を見せていくのでしょうか?
次回もお楽しみに!