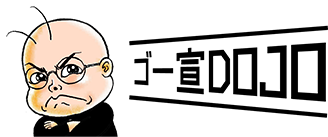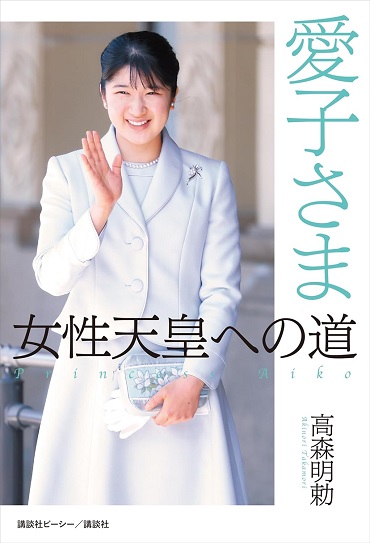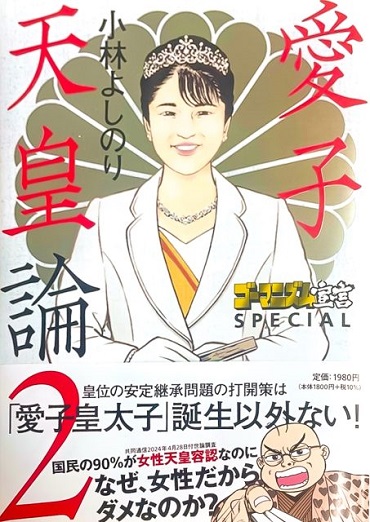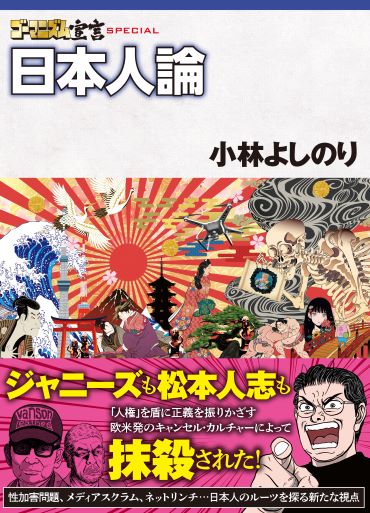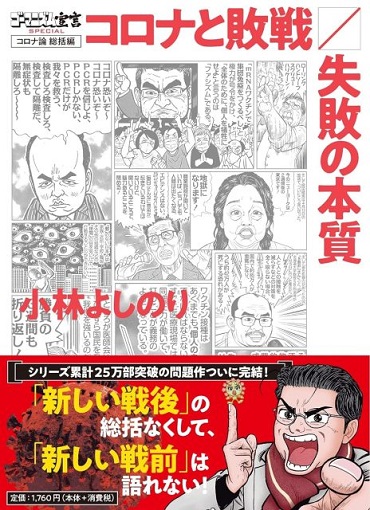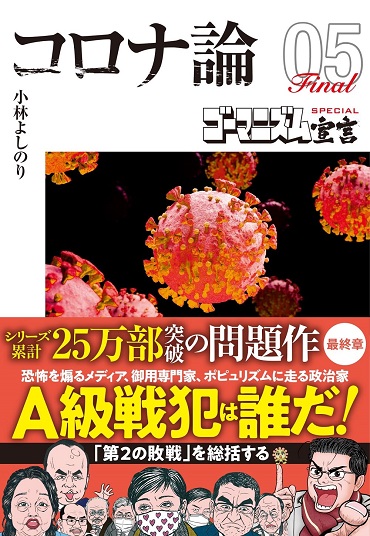政府が国会に検討を委ねている旧宮家系子孫の
養子縁組プランが妥当か否かを判断する場合、
最低限、以下の事実を踏まえる必要があるだろう。①憲法は皇位の「世襲」による継承を求めている。
世襲は親から子への受け継ぎを軸とした血縁による
継承を意味し、男性·女性、男系·女系を全て含む。政府見解は以下の通り。
《憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、
それ以外の皇位継承にが係ることについては、
全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の「皇位は世襲のものであつて」とは、
天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、
皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、
規定していないものと解される。したがって、皇位を世襲とする限り、憲法を改正しなくても、
皇室典範を改正することにより、女系又は女性の皇族が
皇位を継承することを可能とする制度に改めることができる》
(内閣法制局執務資料『憲法関係答弁例集❲2❳』)よって、皇位継承の将来が深刻に危惧される
現実を踏まえるならば、優先的に取り組まれるべき方策は、
皇統に属していて憲法上は当然ながら認められるはずなのに、
専ら「男尊女卑」の観念から女性·女系の皇位継承可能性を
排除している欠陥ルールを是正することだ。②そもそも、旧宮家系子孫は生物学的な意味ならともかく、
厳密には(文化概念としては)「天皇の血統」=皇統に
属するとは言えない。
なので「世襲」の枠外の存在と見るべきだ。「天皇の血統につながる者“のみ”が皇位を継承する」
つまり皇統に属さない者の皇位継承を除外するのであれば、
旧宮家系子孫男性が皇位を継承する可能性に道を開く制度は、
許されないはずだ。③同子孫たる竹田恒泰氏自身が以下のように述べているのは興味深い。
《歴代天皇の男子には「皇統に属する男系の男子」と
「皇統に属さない男系の男子」の2種類があり、
皇位継承権を持つ現職(原文のママ)の皇族は前者に、
また清和源氏·桓武平氏そして私のような旧皇族の子孫などは
後者に該当する》(『伝統と革新』創刊号)更に次のような指摘がある。
《(皇統とは)単に家系的血統を意味するだけでなく、
「皇族範囲内にある」という名分上の意味を包含している》
(里見岸雄氏『天皇法の研究』)④国民の中には旧宮家系に限らず、
生物学的な意味での皇統に繋がる人々は、多く実在すると考えられる。例えば明治時代から昭和20年までに皇籍を離脱した人物は、
清棲家教伯爵から龍田徳彦伯爵まで14人いたが、その子孫は当然、
生物学的な意味での皇統に繋がる。
又、庶子で皇籍になかったものの、北白川宮能久親王の男子だった
二荒芳之伯爵、上野正雄伯爵などの子孫がいたら、それぞれ該当する。更に江戸時代に遡ると、後陽成天皇の皇子が養子に入った
近衛家や一条家、東山天皇の皇子によって創設された
閑院宮家から養子を迎えた鷹司家などは、旧宮家系よりも
「男系」において、天皇との血縁は遥かに近い。それらも全て「皇統に属する」と見て、“男系男子”なら
皇籍取得や皇位継承の可能性を認められるのか。
皇室の「聖域」性や皇位の尊厳を考えると、およそあり得ないだろう。⑤同じく「皇統に属さない」旧宮家系の人々も、
元は皇籍にあった当人ならともかく、「皇族範囲内にある」という
“名分”上の位置付けを元々持たない子孫らを、
上記の人々と区別できる客観的な根拠はあるのか。もし生物学的な“皇統”概念を押し通すならば、
平将門も源頼朝も足利尊氏も皆、紛れもなく
「皇統に属する男系の男子」であって、本来は皇位継承資格を
持っていたことになるだろう。⑥長い皇室の歴史において、「養子縁組」によって
一般国民(臣下)が新しく皇族の身分を取得した事例は皆無だ。《皇族と臣家との養子関係の実例を見ると、
皇族が臣家の継嗣となったときは養家の姓を称するが、
逆に臣家の子女が皇族の養子ないし猶子となった場合は、
それによって皇族に列することはなかった》
(宮内庁書陵部編纂『皇室制度史料 皇族 一』)醍醐天皇の孫に当たる源明子が醍醐皇子·盛明親王との
養子縁組によって「女王」とされたらしいが(『公卿補任』など)、
これは天皇からの血縁が2世という近さ
(今の皇室典範を当てはめると血縁的には内親王)であり、
既に一般国民の血筋になっている旧宮家系子孫男性
(天皇からの血縁が20世以上も離れている)と同列に扱うことは勿論できない。婚姻という心情的·生命的な結合を介することなく、
養子縁組という法律上の手続きだけで“一般国民”の
皇籍取得を認めることは、「皇族」身分それ自体の革命的(!)な変更を意味する。⑦養子縁組以外でも、生まれた時点で皇籍になかった人が、
元は皇族(皇親)だった親が皇籍に復帰した事実を前提として
皇籍を取得した事例として、僅かに平安時代の宇多天皇が
臣籍にあった時に生まれられたお子さま方の
事例(『日本紀略』)があるだけ。親の代から既に皇籍になかった場合に、
後からその子が単独で皇籍を取得した事例は歴史上、
皆無だ(宮内庁書陵部編纂『皇室制度史料 皇 三』)。時折、忠房親王が誤って前例のごとく扱われるが、
生まれた時点では皇籍にあったので、全く事情が異なる
(日本史史料研究会監修·赤坂恒明氏『「王」と呼ばれた皇族』)。⑧旧宮家系子孫男性「養子縁組」プランは、
皇統に属すべき女性·女系を排除し、皇統に属さない
一般国民を婚姻も介さずに皇族とし、
その子孫に皇位継承資格まで認める倒錯的な方策だ。
現実味がないのが救いだが、もしそれが実現すれば
皇統の断絶をもたらす危険性が高い。追記
プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」
今月の2本目は3月28日に公開。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ