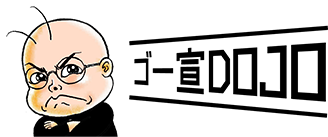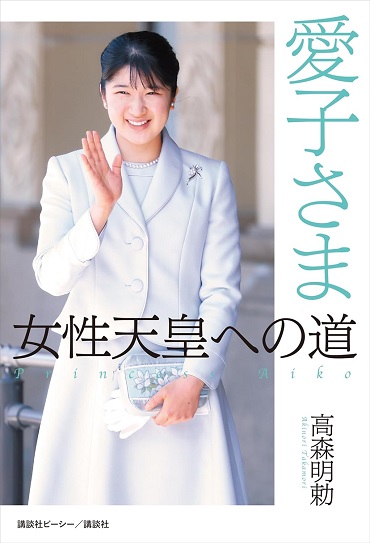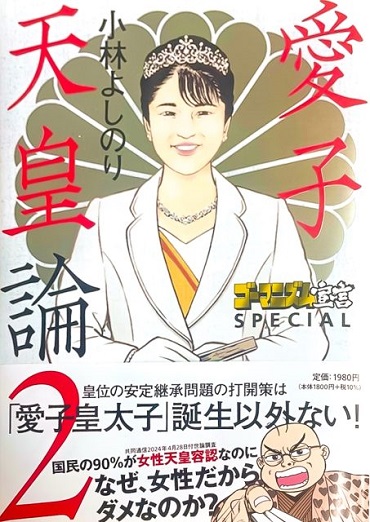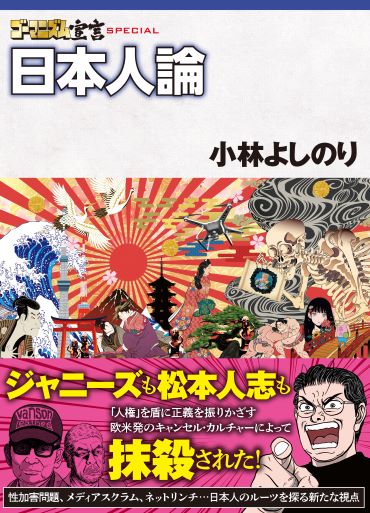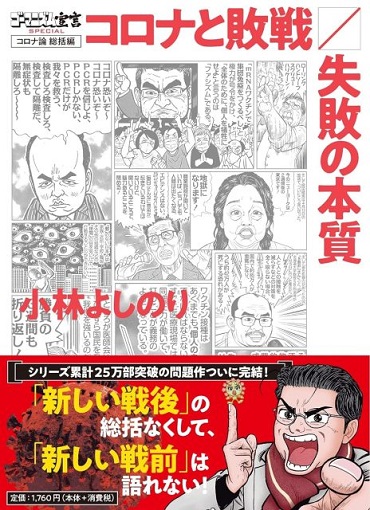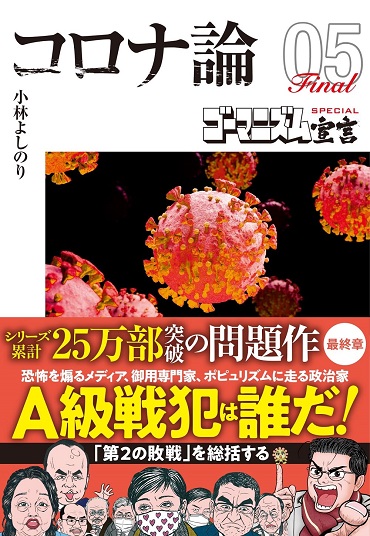徹底比較『フランス革命の省察』の訳し方⑤byケロ坊
8.政治家への評価の基準
上の項目とほぼ同じなのですが、とにかく男系派になってる自称保守は「保守とは何なのか」を一切わかってないので、繰り返し取り上げざるをえません。
こちらはバークによる政治家の評価の基準なので、保守を自認している政治家、特に自民党の国会議員は知っておかなければおかしい部分です。
佐藤健志版(PHP研究所)
「物事をなるべく変えないまま、そのあり方を改善する。これができるかどうかこそ、政治家のよしあしをめぐる評価の基準と言えよう。
現状をひたすら維持するのも、抜本的改革へと猪突猛進するのも、低俗な発想にすぎず、ロクな結果をもたらさないのである。」
二木麻里版(光文社文庫)
「良き愛国者、良き政治家は、すでに自国にある素材をできるだけ活用しようといつも検討するものです。
良き政治家は、改善する能力と保存する傾向を両方もっているものだとわたしは考えています。
そうでない政治家は思考においては低俗、実行においては危険なのです。」
中野好之版(岩波文庫)
「立派な愛国者や真の政治家は、常に現在の彼の故国の素材を如何にすれば最も活用できるか、を考えるはずである。
保存する意向と改良する能力が手を携えることこそ、私の考える政治家の理想像を形成する。これ以外のすべては、着想において通俗であり、実際運用において危険である。」
政治家の人は、本を読む暇も、その気もなさそうですが、特に保守になりたがって男系派をやってる人は、ただニセ保守のネトウヨになっただけという自身の姿を直視したほうがいいでしょう。
男系固執のどこに保存する意向と改良する能力がありますか?
それがない国家運営は低俗で危険だと230年前の本で言われています。
歴史を尊重しつつも、固執でなく、最善を見極めて改善するのが保守の基本というのは、考えてみれば当たり前の話です。
誰もが自分が立脚している現場に照らせば、そういう結論になるでしょうから。
9.『コロナ論』とも共通する病気への対処法について
ここは230年前の病気へのスタンスが、例え話としてですが出てきて興味深かったので取り上げました。
佐藤健志版(PHP研究所)
「それはちょうど、健康を害したからといって、やみくもに特効薬を探し求めるばかりで、毎日の食生活については改善しないのと似ている。
慢性の病気は、生活習慣を改めることで少しずつ治す。革命政府にはこの常識がない。ひょっとしてこれは、たんに愚かなのでなく、人間というものを根本から信じていないせいではあるまいか?」
二木麻里版(光文社文庫)
「かれらはごくありふれたものは利用できないとあきらめてしまっています。治療法のなかに節制をめざす食餌療法などは入っていません。最悪なのはふつうの病気をふつうの療法で治せないとあきらめていること、それもたんに理解力の欠如のせいというより、ある種の性格の悪さのせいにみえることです。そこにわたしは強い懸念をもっています。」
中野好之版(岩波文庫)
「彼らは、日常不断の物事の活用を最初から断念する。食餌療法は彼らの治療体系には存在しない。最も悪いことに、正規な方法にもとづく通常な治療法の彼らの断念は、決して単純な理解の不足だけではなく、或る種の気質的な悪意に由来している。」
ここも佐藤版はわかりやすいですが、原文からかなり変えているのがわかります。
こちらの記述は、病気なんてものは普段の生活習慣や食事から考えるしかないのに、そんなありふれた方法は役に立たないと思ってる、つまりは特効薬を求める人がいるということで、そっくりそのまま今日のワクチン盲信・医者盲信に繋がるものです。
これは(常識的なスタンスとしての)医療もそうで、SNSにいるどこの誰かもわからない医者でなく、DOJOに参加している医療に関わる方は皆さん近いことをおっしゃいます。
コロナやインフルなどの風邪を煽って、ワクチンを推進した人に、理解力の欠如だけではない気質的な悪意があったと言われると、思わず『コロナ論』の読者としては同意もしたくなります。
ただ、気質的な悪意なんて誰でも持ってるとも言えるのですが、今では正しかったということになっているフランス革命を推進した人たちが、保守思想の祖にそうなぞらえられたのだから、基本的に善人に見えがちな医者のことも理解力の欠如と性格の悪さがあるかも…と思っておくのも、自己防衛としては有効でしょう。
「皇位継承の危機から見た『フランス革命の省察』
~男系派が全然保守ではない23の理由」
第1回
プロローグ
1.保守は逆張りではない
2.言葉の中身、論理の有無
第2回
3.設計図の欠陥を指摘すること
4. 「人権はヤバイ」と230年前から言われていた
5.「国をどう動かしていくか」という国家観
6.王と伝統との関係
第3回
7. 王室や伝統だけでなく、キリスト教も弾圧して貶めたフランス革命
8. 「Revolution」は全然カッコいいものじゃなかった
9. 「理性主義」の危険さ
10. 福澤諭吉との共通点(保守としての生き方)
11. 革命派の女性差別に怒る保守主義の父
第4回
12.「オレ様が啓蒙してやる」という態度は非常識なもの
13.固執と改善の話
14.『コロナ論』との共通点
15.愛郷心の大事さ
16.「自由」の意味
17.固執は無能の証
第5回
18.思いっきりリベラルなことも言ってた保守主義の父
19.革命派をカルトに例えるバーク
20.男系闇堕ちした石破と、妥協が技らしい野田のことも言われてる
21.国体を保守すること
22.歴史を省みない“うぬぼれ”
23.頭山満との共通点
徹底比較『フランス革命の省察』の訳し方
第1回
1.「人権は爆弾」と言ってるところ
第2回
2.革命派・人権派による王室否定と女性差別の指摘
3.「prejudice」の訳し方
第3回
4.常識が失われることへの警戒
5.困難に立ち向かうこと
第4回
6.自国の歴史を省みないのはうぬぼれ
7.迷信に執着するのは保守ではない
フジテレビの首脳陣を10時間吊るし上げた記者たちの狂態を見ていると、フランス革命に熱狂した民衆もこんなもんだったんだろうなあと思えてきます。
あの中継を見た人の間では「さすがにあの記者たちは酷い」といった反響が支配的になっているところは、まだ救いであるとは言えるのでしょうが。
問題はそういう革命願望・破壊衝動を持っている者は、自分自身の姿を絶対に直視しないということで、それも時間を超え、国を超えても全く変わりません。
だからこそ、事あるごとにバークの言葉に納得するばかりです。