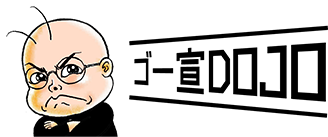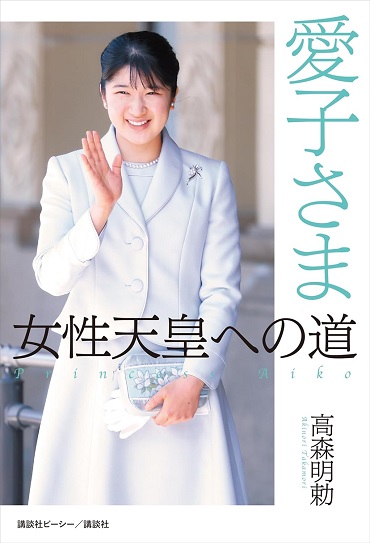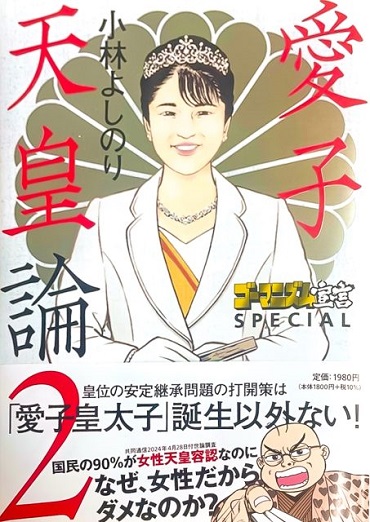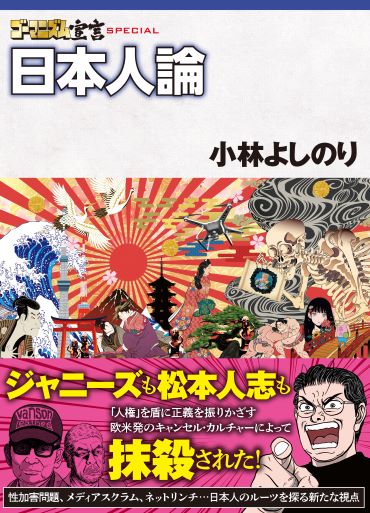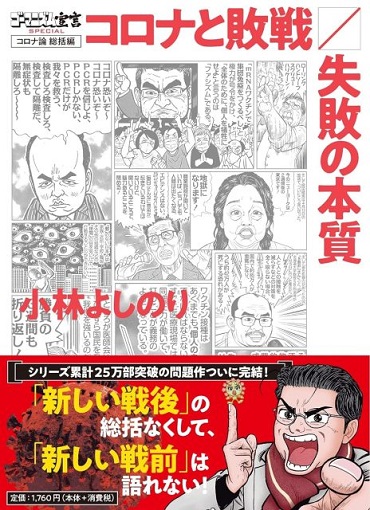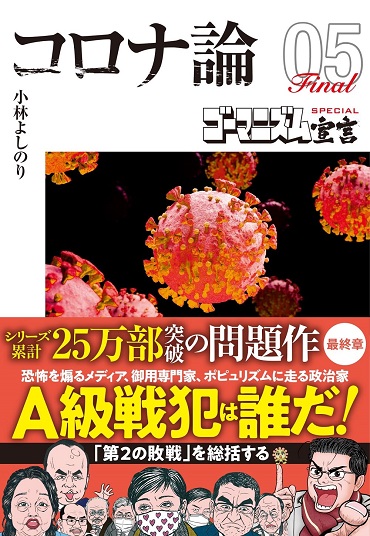「光る君へ」と読む「源氏物語」第8回 第八帖<花宴 はなのえん>byまいこ
愛子さまが5月11日に「夢みる光源氏」展を御鑑賞の際、解説を担当した国立公文書館の調査員に、高校時代のレポートで『枕草子』に登場する犬「翁丸」をテーマに取りあげられたことを明かされたとFNNが報じました。FNNはさらに、―この「翁丸」の一節が、西暦995年に藤原隆家が花山法皇を襲撃した「長徳の変」が背景になっているのではないか、ということについてレポートで論じたという愛子さま。「長徳の変」の場面を展示していた『栄花物語』の前では、「大変思い入れがある場面です」と話されたそうだ。―と、レポートの内容と展示へのご感想を伝えています。
https://www.fnn.jp/articles/-/698355
愛子さまが御鑑賞された日の翌日、5月12日に放送された「光る君へ」第19回は、藤原伊周(三浦翔平さん)が斉信(金田哲さん)の父・為光(阪田マサノブさん)の四の君(四女)に通おうとしたところ、花山院(三本郷奏多さん)の牛車が停まっているのを見て、逆上。報復のため弟の隆家(竜星涼さん)が矢を射かけるも、花山院の相手は、三の君(三女)だった…という「長徳の変」の発端が描かれました。
愛子さまがレポートで取り上げられた「翁丸」の一節は、『枕草子』「上にさぶらふ御猫は」から始まる第7段にあり、一条天皇の愛猫に吠えかけた「翁丸」という犬が島流しになるも、宮中に戻ってきて涙を流し、許されるという描写がなされています。
花山院に矢を射かけた「長徳の変」により、藤原伊周、隆家は流罪となり、後に許されて帰京します。清少納言は『枕草子』で「長徳の変」への言及はしていない代わりに、「翁丸」で中関白家(関白藤原道隆を祖とする一族)の悲劇を暗に示したのでしょうか。愛子さまのレポート、拝読してみたいですね。
「源氏物語」には、光る君と頭中将が同じ女性に想いをかけたり、鉢合わせするなど、恋のさや当てと呼べそうなシーンがあります。物の怪に手をかけられた夕顔は、頭中将の恋人でしたし、末摘花の住む常陸宮邸の庭や、源典侍の寝所でも、二人は出くわすことになりました。頭中将は、左大臣の父と、桐壺帝の妹を母に持ち、「紅葉賀」の帖で青海波を舞うほどの貴公子、光る君のライバルを自認して、歌舞音曲でも、恋でも張り合っています。
伊周も、花山院と恋のさや当てをしている、もしくは譲るくらいの余裕をもっていれば、あの短絡的な行動にはならず、「長徳の変」も起きなかったかもしれません。
今回は、「源氏物語」に伊周の陥った危機が反映されていると言われる所以の、光る君が絶体絶命に陥る発端をみてみましょう。
第八帖 <花宴 はなのえん (桜の花の宴)>
二月の二十日頃(旧暦 新暦では約一か月後の三月下旬)、宮中で桜の花の宴が催され、中宮となった藤壺は、弘徽殿の女御よりも上座に座ります。弘徽殿の女御は心中穏やかではありません。宴では作詩のための文字を与えられて漢詩を作ることになり、光る君は「春という文字をいただきました」という声さえ、一段と優っているのでした。
春鶯囀(しゅんのうでん 雅楽で唐の時代に伝来した唐楽の1つ 唐の第3代皇帝・高宗が作らせたと言われ、ウグイスのさえずりを模した旋律を用いる)の舞が面白く見られたときには、光る君は東宮から紅葉賀の際に披露した舞を所望されたので、袖を翻すところを一節、舞います。頭中将も桐壺帝から促されて柳花苑(りゅうかえん 唐楽の1つ 四人の女舞だったが平安期に絶え、現在は管弦のみで演奏される)の舞を披露し、夜が更けてから桜の花の宴は終わりました。
月が明るく美しく上り、光る君は酔い心地に去りがたく、藤壺の住まうあたりをさまよい歩きますが、戸口は鎖されています。そのまま弘徽殿の細殿(ほそどの 屋根付き渡り廊下、または殿舎の細長い廂の間 弘徽殿と登華殿の場合は、西側の廂の間のことで、簀子・濡れ縁がなく、戸から直に入れる)の近くに立ち寄ると、戸口が開いていました。
弘徽殿の女御は、宴が終わった後に上の御局(うえのみつぼね 帝の日常生活の場・清涼殿の隣にあり、妃が召された場合に赴く)に上られたので、人が少なく、奥の枢戸(くるるど 開き戸)も開いています。光る君が細殿に上って覗いてみると、若く美しい声で、並の身分とは思われない女性が「朧月夜に似るものぞなき」と口ずさみながら、こちらの方にやって来るではありませんか。光る君は、その女性の袖をとらえ、そっと抱き上げておろすと戸を閉めてしまいます。
驚いて茫然としている女性は、とても愛らしく、「ここに人が」と言うのですが、「わたしは何をしても許されているから、人を呼んでもどうにもなりませんよ」との声で光る君と気づき、少し安心したようでした。
女性を愛しんでいるうちに夜が明けたので、光る君が「どうか名のってください。文を差し上げるにはどうしたらいいのか、これで終りとは、まさか思っていないでしょう?」と言うと
うき身世に やがて消えなば 尋ねても 草の原をば 問はじとや思ふ 朧月夜
幸い薄き身の私 このまま儚く消えたなら 草の原わけても 墓を訪ねてはくれないの?
「たしかに。これは言い間違えましたね」などと言ううちに、人々が起き出してきたので、扇を交換して別れます。光る君は、「美しい人だった。きっと弘徽殿の女御の妹だろう。恋は初めての様子だったので、右大臣の姫のうち五の君か六の君か、もし東宮(とうぐう 皇太子)に嫁ぐ予定の六の君・朧月夜(おぼろつきよ)だったら可哀そうなことをした」などと思っています。
その日は桜の花の宴に続いて後宴(大きな宴の後の小宴会)があり、光る君は筝の琴(そうのこと 唐から伝来した雅楽を演奏する楽器 琴柱で弦の音程を調節する)を弾きました。藤壺は、暁の頃に上の御局に上ります。光る君は、あの美しい女性が宮中から退出したか気になって、従者を見張らせていると、弘徽殿から、見るからに身分の高そうな様子の牛車が出ていったと知らされました。右大臣のどの姫だったのかと、光る君は思い悩んでいます。
あの女性は、はかない夢のような光る君との逢瀬を思い出しては、切なく感じていましたが、父の右大臣が東宮に入内させようと決めているので、どうしようもありません。
三月の二十日頃(新暦では四月下旬)、光る君は宮中にいたときに、右大臣から藤の花の宴の誘いを受けました。桐壺帝も宴に行くように促したので、光る君は衣装を整えて出かけてゆき、夜が次第に更ける頃、酔ったふりをして席を立ち、寝殿の東側の戸口にもたれて座りました。
「酒を強いられて困っているのです。物陰にでもわたしを隠してくださいませんか」と光る君が妻戸(寝殿造の両開きの扉)の御簾をくぐり、頭の方から身をさし入れると、女房たちは上品な様子で、空薫物(そらだきもの 前もって、もしくは別室で焚く香 どこからともなく漂うのが良いとされる)が煙たいほど香っています。「扇を取られて辛き目を見る」と光る君がおどけた声でいうと、ため息が聞こえたので、近づいて几帳越しに手をとらえて、
梓弓 いるさの山に惑ふかな ほの見し月の影や見ゆると 光る君
月照らす いるさの山で惑うのです ほの見えた月影のような あなたに会えはしないかと
心いる方ならませば 弓張の月なき空に 迷はましやは 朧月夜
わたくしを求める心があるならば 月なき空であろうとも 迷いはしないはずでしょう
という声は、まさにあの女性、朧月夜だったのでした。
*梓弓(あずさゆみ)射る(いる)の枕詞 「いるさの山」にかかる *いるさの山 但馬国(兵庫県)にあるという山 歌枕(和歌の題材となる名所旧跡)*弓張の月 弓を張ったような形の月 半月 下弦の月 上弦の月
***
「光る君へ」第6回、ききょう(ファーストサマーウイカさん)・清少納言と、まひろ(吉高由里子さん)・紫式部が出会う機会となった漢詩の会は、「酒」という文字が作詩のために提示されていました。また、第19回で、まひろがききょうの案内で登華殿にいたところ、一条天皇が颯爽と現れて定子と塗籠(ぬりごめ 厚い壁で仕切られた部屋 寝室としても使われる)に入る場面は、『枕草子』「淑景舎(しげいしゃ)東宮に」から始まる89段に描かれた定子が昼も夜も一条天皇に召される姿の再現のように思います。
二人の才女の交流が実際にあったのかどうかは、定かではありませんが、「源氏物語」で弘徽殿の女御と藤壺の中宮が、相次いで上の御局に上り、桐壺帝に召されていると描かれているのは、ききょうが言った台詞のように「重いご使命を担っておられる」、それほど重要な務めであり、女房として彰子に仕えることになる紫式部(仕えていた当時の女房名は藤式部)も、宮中で目にしていたことだったのでしょう。
そんな宮中で、チャンスとばかり光る君はさまよい、異母兄である東宮の妃となるはずの女性と関係してしまったのは、よく確認すれば防げたかもしれない、伊周と同じようなうっかりミスと言えるかもしれません。しかも東宮は、宴で舞を所望するほど、光る君に好意を寄せているというのに。
とはいえ、朧月夜の魅力に出会って、果たして恋をしないでいられるものでしょうか。弘徽殿の西廂、戸も開いて月明かりも射していたと思われる場所で、「朧月夜に似るものぞなき」と口ずさんだ言葉、そのままの美女がひとり。
朧月夜の言葉は、平安時代初期の歌人・大江千里の「照りもせず 曇りもはてぬ 春の夜の 朧月夜にしくものぞなき」「照ることも曇りきってしまうこともない 春の夜の ぼんやりとかすむ朧な月夜に及ぶものはない」から。月明かりと共にお酒の力もあって、さらに女性を魅力的に感じられた光る君は、夜もすがら、人々が起き出すまで一緒にいて、相当に夢中になっていたのでしょう。
「光る君へ」で、道長とまひろが「なにがしの院」を思わせる荒れはてた邸で結ばれるときも、離れた場所で二人が互いを想い合うときも、夜空には月。闇夜ではなく、灯りがなくとも朧にみえる月明かりは、まさに陰翳礼讃。けざやかに隈なく照らすのではなく、互いを美しく浮かび上がらせる柔らかな光は、デモニッシュな陶酔感をもたらしているように。
桜の花の宴が催されたのは、旧暦の二月の二十日過ぎ、藤の花の宴は三月の二十日過ぎ。旧暦は、一日は新月、十五日は満月というように、月の満ち欠けと連動しており、光る君と朧月夜が逢った二夜は、同じ形の下弦の月、「弓張の月」が上っていたのでしょう。
五の君か、六の君か、名のらず別れてしまった朧月夜。今回も、空蝉や夕顔と同じく、想いの高まったところで会えなくなるという、藤壺との関係の再現性によって忘れ得ぬ女性となる恋のパターンであり、道長とまひろとの関係にも通います。
朧月夜は、実は光る君を待ち伏せしていたのではないかという考え方もあります。「光る君へ」で打毬(だきゅう)に興じる道長、公任、斉信、直秀を見学した女性陣が、「雨夜の品定め」のように男性陣の品評会をした際に、倫子(黒木華さん)は道長に高評価をつけてロックオン、晴れて正妻となりました。
朧月夜も、桜の花の宴の際に高評価をつけて網を張り、光る君は絡めとられてしまっていたのだとしたら。別れ際の振る舞いにしても、手に入れるのが難しくて謎めいていた方が、光る君が熱心になるということも、分かっていたような感じもします。
光る君を夢中にさせた天性の恋の手練れ・朧月夜。二人はどうなってゆくのでしょうか。
「光る君へ」と読む「源氏物語」
第1回 第一帖<桐壺 きりつぼ>
第2回 第二帖<帚木 ははきぎ>
第3回 第三帖<空蝉 うつせみ>
第4回 第四帖<夕顔 ゆうがお>
第5回 第五帖<若紫 わかむらさき>
第6回 第六帖<末摘花 すえつむはな>
第7回 第七帖<紅葉賀 もみじのが>
月や月明りの薄暗さが、なんとも言えない情緒を作り出しているということが、よくわかります。
そう思うと、最近ではテレビカメラの性能が良くなりすぎて、何でもくっきり鮮明に映し出されてしまうので、かえって薄暗い中のぼんやりした情景の描写がしづらくなっているのではないかと『光る君へ』を見ながらつい思ってしまうのですが、これは文章でないと表現できないものなのでしょうか?