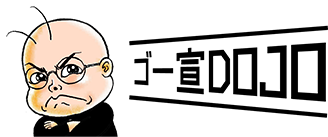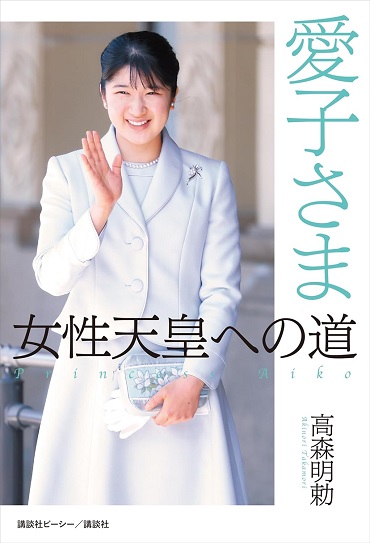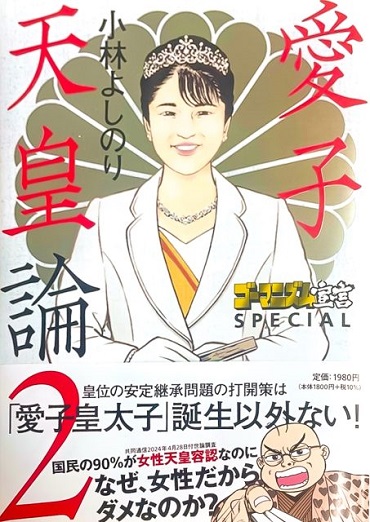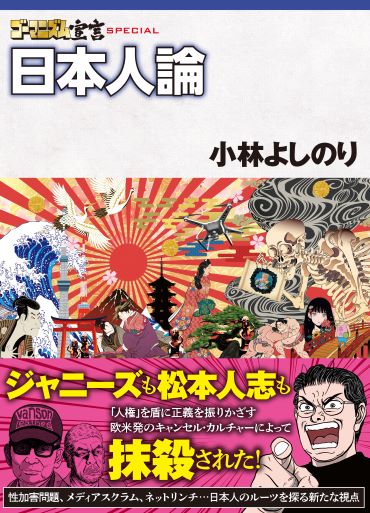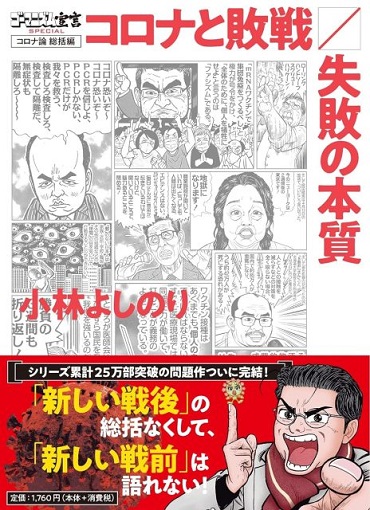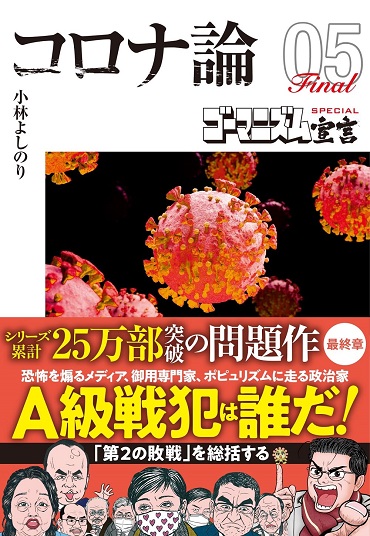「光る君へ」と読む「源氏物語」第7回 第七帖<紅葉賀 もみじのが>byまいこ
愛子さまは4月15日に皇居で開かれた宮内庁楽部による春季雅楽演奏会をご鑑賞になりました。―演奏会では、笙(しょう)や篳篥(ひちりき)、笛などによる「管絃(かんげん)」と、演奏に合わせて舞う「舞楽」が披露された。愛子さまは担当者の説明に耳を傾け、舞楽の所作や意味合いなどについて尋ねられた。終了後「とても楽しみました」と感想を述べられた。―と日本経済新聞は報じています。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE1418Q0U4A410C2000000/
「光る君へ」で、まひろが倫子(黒木華さん)の代わりに引き受けた「五節の舞」は日本の雅楽で唯一、女性が演じる舞で、花山天皇の大嘗祭(だいじょうさい 皇位継承の際の宮中行事)の豊明節会(とよあかりのせちえ 大嘗祭の後の饗宴)の際に、四人の姫が舞を披露していました。「源氏物語」には、五節の舞姫に選ばれる女性や、「五節」と呼ばれる女性が登場しているので、まひろ・紫式部本人が舞姫だった、というドラマの設定は、斬新かつ納得できるものでした。
雅楽について調べると、大宝律令の制定(701年)で治部省に属する機関として雅楽寮が設けられ、日本固有の歌舞(管弦と舞楽)や大陸の国々から伝来した外来歌舞の演奏を担当。「光る君へ」で描かれた能、狂言、文楽に多大な影響を与えた散楽は、雅楽寮の散楽戸で保護されていた時期があり、東大寺大仏開眼供養法会(752年)で、他の芸能と共に奉納されたとのこと。
ウィキペディアの「散楽」の項に「『続日本紀』には、天平7年(735年)に聖武天皇が唐人による唐・新羅の音楽の演奏と弄槍の軽業芸を見たという記述がある。これが、散楽についての最初の記録とされる」とあります。こういった記録が残り、芸能の歴史が連綿と続き、豊饒なる文化が形作られたのは、日本が天皇を戴いてきたからこそ。愛子さまがご鑑賞になるものは、これから全て、連綿と続く日本の歴史に、さらなる一ページを刻めるということになりますね。
今回は、光る君とライバル頭中将が挑む宮中での雅楽の場面から始まります。
第七帖 <紅葉賀 もみじのが(紅葉の頃に行われる祝宴)>
紅葉の頃、桐壺の帝は朱雀院への行幸の催しを、懐妊している藤壺にも見せたいと、宮中の庭で試楽(しがく 雅楽の予行演習)を行います。光る君は頭中将と共に、「青海波(せいがいは 雅楽の演目 袖を振りながら二人で舞う 衣装の波型の染模様も青海波と呼ばれ江戸時代に流行)」を舞いました。集まった人々は感動の涙を流し、弘徽殿の女御は「神などが空から愛でるような。気味が悪くて不吉だこと」と光る君を妬んで言うほどの美しさです。朱雀院への行幸の催しの当日も、「青海波」は大成功をおさめ、その夜、光る君は正三位(大納言相当)に、頭中将は正四位下(頭中将の位階は正四位上・下 従四位上・下)に昇進しました。
二条の邸にいる若紫はすっかり光る君に馴染んでいました。藤壺の兄で若紫の父の兵部卿宮は、三条の宮(兵部卿宮の邸)に出産で里下がりした藤壺の様子を伺いに来た光る君が娘の婿とは知らないままに「女性にして見ていたい」と色好みな心で思っています。
元日となって、若紫はひとつ歳をとり(数え年 生まれた時に1歳、元日を迎える度に1歳年を取る1950年頃まで使われていた年齢の数え方)11歳になりましたが、光る君が夫であると乳母の少納言から聞かされても、いまだに人形遊びをする幼さを残しています。光る君は19歳、娘を育てるような気持ちで若紫に琴や書などを教えています。正妻の葵上は若紫の噂を聞いて、ますます心を閉ざし、左大臣は、めったに足を運ばない光る君を残念に思いながらも、あれこれと世話をしては、その美しい姿を見ることに生きがいを感じています。
ふた月遅れで、藤壺に皇子が誕生しました。あまりにも光る君に似ているので藤壺は恐ろしくなりますが、桐壺帝は「幼いうちはこのように皆、似ているのだろうか」と、ただ喜びを見せています。光る君の心は、恐ろしさや嬉しさや様々な感情で揺れ動くのでした。
その頃、宮中に仕えて尊敬されつつも、かなり年配でありながら非常に色好みな女性、源典侍(げんのないしのすけ 典侍は後宮の内侍司の次官)がいました。光る君は、57,8歳になる源典侍の色好みに興味を覚えて関係を持ちましたが、それに対抗して頭中将までが言い寄ります。ある夜、光る君と頭中将は、源典侍の寝所で鉢合わせ。源典侍が慌てて騒ぐなか、光る君と頭中将は、ふざけて衣を引っ張り合って乱闘したあげく、互いに袖や帯が取れたしまりのない姿で、一緒に帰ってゆくのでした。
翌朝、源典侍から歌が光る君に届けられます。
恨みても いふかいひぞなき たちかさね 引きてかへりし 波のなごりに
恨んでも仕方ありませんわね 幾重にも引いてはかえす波のように お二人が来ては帰ってしまったのは
光る君と頭中将は、日が高くなってから宮中に出仕し、すまして公事(くじ 朝廷の儀式・行事 政務)を行っているのを、お互い可笑しく思っています。
桐壺帝は、譲位を考え始め、藤壺の産んだ皇子を次の東宮にするため、後見として光る君を宰相(さいしょう 太政官の官職・参議の唐名 参議は朝政に参加するという意味もあり、現在の参議院はこの言葉に由来する)に、藤壺を中宮(ちゅうぐう)にしました。弘徽殿の女御は心おだやかになれませんが、桐壺帝は「東宮の御代になれば、あなたは皇太后になれるのだから」となだめます。藤壺はさらに手が届かない存在になってしまい、光る君は、切なくなるのでした。
***
「光る君へ」で、藤原伊周(三浦翔平さん)と弟の隆家(竜星涼さん)の2人が、登華殿(後宮の殿舎)で定子(高畑充希さん)の琴と一条天皇(塩野瑛久さん)の横笛に合わせて舞を披露していたところ、詮子(吉田羊さん)が「御上、先ほどの騒々しい舞は何ごとでございますの?」と諫める場面は、「紅葉賀」の冒頭が髣髴といたしました。また、「東宮の御代になれば、あなたは皇太后になれるのだから」という桐壺帝の言葉は、円融帝(坂東巳之助さん)が「そなたは 国母(こくも)となるやもしれぬ立場」と言い、詮子を女御に据え置いたことと重なります。
「青海波」を美しく舞った夜に、光る君と頭中将が昇進するというのは、アメノウズメの舞が披露されて以来、芸能が重んじられてきた日本ならではの表現のように思います。弘徽殿の女御からは「気味が悪い」と妬まれる光る君の美しさは、兵部卿宮にとっては第二帖の「雨夜の品定め」の際の表現と同じく「女性にして見ていたい」、左大臣にとっては「姿を見ることに生きがいを感じる」ほど。舅の立場にある二人を夢中にさせる男性の美しさを描き込んだ1000年前の「源氏物語」を読んでも、「光る君へ」で光る君のモデルと言われる伊周や一条天皇を演じる現代の俳優さんたちの女性に見紛うような美しさをみても、日本の性の境界は古今、曖昧なのだなあと感じます。
とうとう藤壺が光る君そっくりの皇子を産みました。桐壺帝が喜び、藤壺と光る君が心苛まれる場面、読んでいる方もドキドキします。桐壺帝はコキュだったのか、密通に気づいていたのか。歌舞伎「源氏物語」で桐壺帝を演じられた故・12代目市川團十郎さんは、密通に気づいているという解釈をしておられたようです。
コキュ、近年ではNTR、ネトラレと表現される「寝取られ問題」、フランスの哲学者シャルル・フーリエの著した「四運動の理論」には、①「コキュ(カッコウ 托卵することから)妻に間男されて気づかない夫」、②「コルネット(頭巾をかぶった)妻に間男されても許す夫」、③「コルナール(角をはやした)妻に間男されて怒り騒ぐ夫」の3つが紹介されています。
「源氏物語」に登場した例としては、空蝉の夫・伊予介は、①のようでしたけれども、田辺聖子さんは②のパターンでパロディを描いておられます。夕顔の恋人・頭中将は①、藤壺を中宮にした桐壺帝は①もしくは②ということになるでしょうか。今のところ、光る君は間男をしている側に立っていますが、妻に間男されたときに、どうなってゆくかも、後の帖で紫式部は描いています。
深刻な場面の後に、息抜きのごとく登場する源典侍。光る君と同じ姓の源典侍は、藤壺を光る君に手引きした王命婦のように「帝の血を引く」女性なのでしょう。二人の貴公子を寝所に迎え、まさに「けんかをやめて」状態だった翌朝、「恨みても」と詠んだ歌は、モテてしまって得意気、とっても嬉しそう。
19歳の光る君と、57,8歳の源典侍とは、40歳ちかい年齢差。現在、放送中の江國香織さん原作のドラマ「東京タワー」は、King & Princeの永瀬廉さん演じる21歳の医大生と、「光る君へ」で道隆の妻・貴子役をされた板谷由夏さんが演じる45歳の建築家との恋愛模様が描かれています。永瀬さんの友人役・Travis Japan の松田元太さんが対抗意識を燃やしてMEGUMIさん演じる年上の女性に迫るところなど、光る君に対する頭中将のようで面白く思いつつ、1000年前の年齢設定の大胆さに改めて感じ入りました。
さて、光る君は宰相・参議になりました。「光る君へ」で、実資(秋山竜次さん)が優秀過ぎて、円融天皇、花山天皇、一条天皇と続いて蔵人頭(天皇の傍に仕える蔵人所のトップ)に任じられ、なかなか参議になれずに憤ったり(989年・33歳で参議に昇進)、道長(柄本佑さん)が右大臣となったときに、蔵人頭の斉信(金田哲さん)が「俺もそろそろ参議にして欲しいなあ」と言ったり(996年・30歳で参議)と、朝政に参加できる官職・参議になるのは、貴族たちにとって重要なことだったのでしょう。
「光る君へ」で伊周(三浦翔平さん)は、あまりにも早く昇進して(991年・18歳で参議)反感を持たれていましたが、桐壺帝が光る君を宰相・参議にしたのは19歳で同じような年齢。早い昇進は悲劇を招くということも、紫式部は示唆しているのかもしれません。
19歳の光る君の恋愛対象が10,11歳から57,8歳まで
というところに驚かされます。本当に大胆!
深刻な場面の後に少しコミカルに源典侍のシーンが
入ってくるというのも面白いです。
『光る君へ』でも、ドラマの中の緩急のつけ方が
非常にうまいと思って見ているのですが、
そういうところも意識して作られているのでしょうか。
大人気連載、次回もお楽しみに!