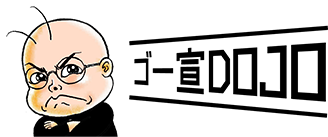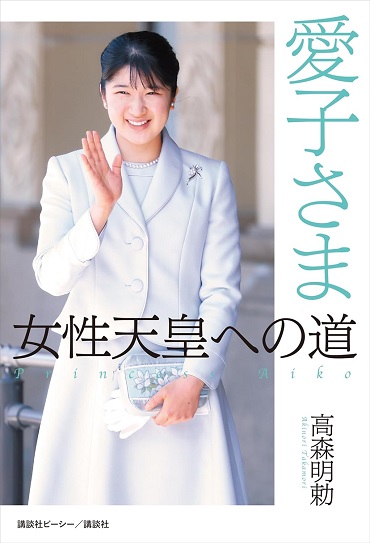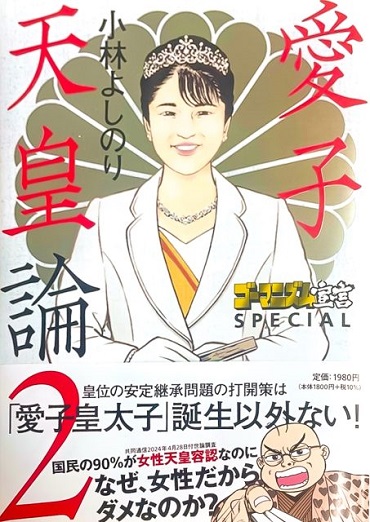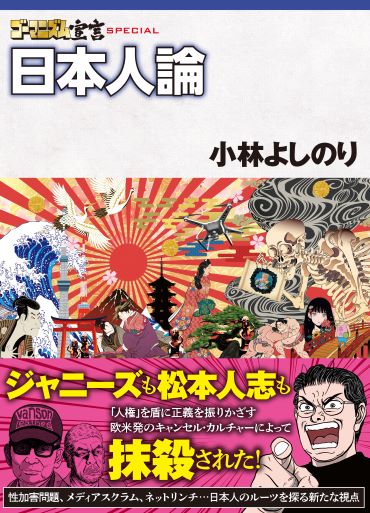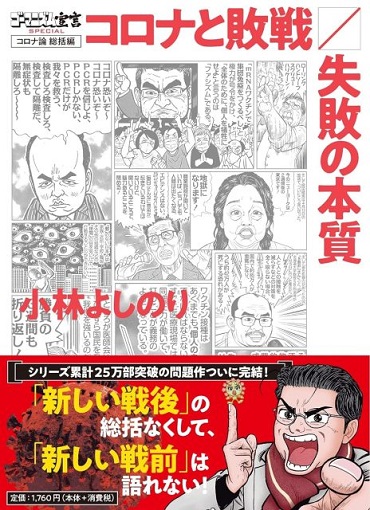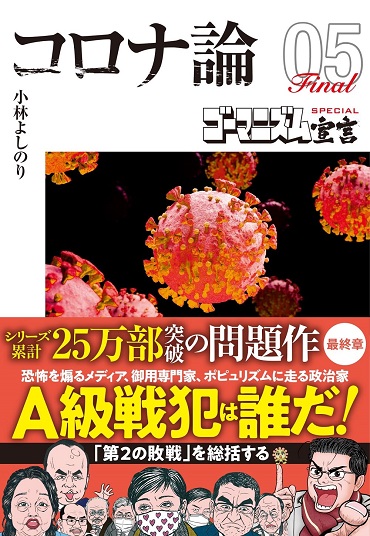「光る君へ」と読む「源氏物語」第6回 第六帖<末摘花 すえつむはな>
「光る君へ」には、まひろの父・藤原為時(岸谷五朗さん)が官職を得られないと、家の雨漏りを直すこともできず、使用人たちが次々に去ってゆき、まひろが就職活動をしても、父に官職がないと門前払いをされる様子が描かれました。
道長が悲田院(貧しい人や孤児を救済する最古の福祉施設)で病に倒れたまひろを送り届け、看病する有り様を見た為時が「これをご縁にお前のお世話をしていただくことは出来ぬであろうか?」と言ったのは、女性の親に官職や財産がなければ、なかなか縁づけられないということ。
「枕草子」の「すさまじきもの 除目(じもく)に司得ぬ人の家(興ざめなもの 任官の儀式で官職を得られなかった人の家)」とは、まさにこういうことなのだなあと。
道長が右大臣で内覧(ないらん 天皇に奏上する文書を事前に読み処理する役職)となった翌年、為時は越前守となりました。後にまひろが紫式部として、道長の娘・彰子に仕えることが出来るようになるのも、結婚できるようになるのも、父・為時が官職を得たことも大きく影響していると思います。
今回は、「帝の血を引く」高貴な女性が父を亡くした後、どうなるかもみてみましょう。
第六帖 <末摘花 すえつむはな (紅花の別名 赤い鼻の女性)>
夕顔や空蝉を忘れられない光る君は、打ち解けた付き合いのできる女性を探し続けていました。惟光の母とは別の光る君の乳母の娘・大輔の命婦(たいふのみょうぶ)は、宮中に女房として仕えており、皇族の血を引く父親の兵部の大輔が故・常陸宮の邸に住んでいた縁で、命婦も里下がりの際は身を寄せています。命婦は宮中で光る君と話した際に、常陸宮の晩年に生れた姫・末摘花が父宮の死後は心細い暮らしをしながら、琴に親しんでいると伝えました。心ひかれた光る君は、宮中からの帰りに常陸宮邸を訪れ、琴の音を聴きたいと願います。
大輔の命婦は自分の部屋に光る君を通してから、寝殿(主人の住まい)に赴いて末摘花を促すと、すぐに琴がかき鳴らされます。琴の音はすぐに止んでしまったので、物足りない光る君は末摘花の姿を見ようと寝殿に近づくと、壊れた透垣(すいがい 板や竹で編んだ垣根 隙間があるので垣間見が出来る)の傍で頭中将に出くわしました。宮中から一緒に退出した光る君が、左大臣邸にも二条の自邸にも行こうとしていないので後をつけてきた頭中将は、琴の音を聴きつつ待ちぶせしていたのです。二人は同じ車(牛車 ぎっしゃ 牛にひかせる車)に乗り、横笛を吹き合いながら左大臣邸に行くことになりました。
左大臣邸でも笛を吹く二人に左大臣は高麗笛を合わせ、女房たちにも楽器を弾かせました。琵琶の上手な女房・中務の君(なかつかさのきみ)は、頭中将が言い寄るのを断って、光る君と時おり関係を持っています。左大臣の正妻・大宮(おおみや 桐壺帝の妹)にも知られて居づらくなっていますが、左大臣邸を去れば光る君と会えなくなるので思い切ることができません。
光る君も頭中将も、さきほど聴いた琴の音や、もの寂しく心ひかれる住まいの有り様を思い出しています。二人は張り合うように、それぞれ末摘花に文を出しますが、やはり返事は来ないまま。頭中将まで文を出した様子に、光る君は嘆かわしくなって大輔の命婦に相談すると「ひたすら控えめで引っ込み思案なのは珍しいほどの方なのです」とのこと。光る君は、はかなげだった夕顔を思い出してしまうのでした。
それからも光る君は何度も文を届けますが、末摘花からはいっこうに返事が来ません。悔しくなった光る君が、再び常陸宮邸を訪れたので、大輔の命婦は廂の間の襖をしっかりと閉ざして末摘花のそばに通しました。様々に話しかけたり、歌を詠みかけたりしても、やはり返事がないので、とうとう光る君は襖を押し開けて中へ入ってしまいます。大輔の命婦は末摘花を気の毒に思いながらも自分の部屋に戻り、女房たちも世に類いなき美しい光る君を咎めて騒ぎ立てたり嘆いたりはしないのでした。
光る君と関係を持っても、ただ我を失い恥ずかしがるばかりの末摘花。世なれぬ高貴な姫にとっては初めてのことだからと大目に見ながらも、光る君はため息をつきつつ夜が明けないうちに帰ります。光る君は日が暮れてから、ようやく後朝(衣衣)の歌(きぬぎぬのうた 衣を重ねて共寝をした翌朝に男性が送る歌 早く送るほど良い)を送りますが、末摘花からの返歌は侍従という女房の代作、古びた紙に、行の上下を揃えて力強く書く少し古い書法で、見る甲斐もありません。それでも光る君は、間を繋いでくれた大輔の命婦を気にかけて、ときどきは通っています。
ある雪の朝、光る君は末摘花の姿をまざまざと目にしてしまいます。胴長で、象のように長い鼻の先は垂れ下がって赤く、額は広く下ぶくれなのに顔は非常に長く、体は痩せすぎています。髪はとても長く美しいものの、古くなったみすぼらしい衣の上に、香をたきしめた黒貂の皮衣(ふるきのかわぎぬ 黒い貂てんの毛皮)を着ているのは古風で若い女性には相応しくありませんが、よほど寒いのだろうと思われる青白い顔色です。
「わたしでなければ、堪えきれないだろう。こうして通うようになったのは、故・常陸宮の魂の導きかもしれない」ありふれた姿ならば忘れてしまうところ、かえって光る君は心が動かされて、皮衣に代わる絹、錦、綿や女房たちの衣などを贈り、こまやかに世話をすることにします。
年が暮れて、宮中で大輔の命婦に会った光る君は、末摘花からの歌をしたためた文と元日の装束を受け取りますが、古風な歌の詠みぶりと、耐えがたいほど古びて艶のない衣を見てあきれてしまいました。
から衣 君が心のつらければ
袂はかくぞ そぼちつつのみ 末摘花
唐衣(衣服に関する物や音にかかる枕詞)あなたの心が冷たいので わたしの袖の袂は涙に濡れております
末摘花の文の端に、手すさびに光る君は歌を書きつけました。
なつかしき 色ともなしに 何にこの末摘花を 袖に触れけむ 光る君
心ひかれる色でもないのに どうしてこの赤いはなに 袖をふれたのだろう
光る君の歌を目にした大輔の命婦は、末摘花の容貌を思い合わせて可笑しく思います。
元日から数日たって二条の邸に行ってみると、若紫はとても美しく、光る君は雛遊びや絵を描いて一緒に遊びます。鏡を見ながら光る君がわざと鼻を赤く染めたのを、若紫が心配して拭おうとしたりして、仲の良い兄妹のような二人なのでした。
***
第二帖の「雨夜の品定め」で「高貴な家柄から落ちぶれたり、受領(地方長官・知事)に任命されて成りあがったりした中流の家の女性たち」に興味を抱いた光る君は、空蝉、夕顔に続いて、末摘花と関係を持ちました。空蝉と夕顔とは、また会ってみたいと感じられる交歓ができましたが、末摘花とは、それには至らなかった模様。
末摘花が、女房の侍従の代作を古びた紙に行の上下を揃えて書いたのは、父宮の遺した古い身の周りの品を大切にして古風な流儀を守っている、言い換えれば新しい紙を手に入れるほど経済に余裕がなく、世情にも疎いということ。通常は正妻の立場の女性が用意する正月の装束を届けたことや、「唐衣」という万葉集から使われている古色蒼然とした枕詞の歌も、光る君からすれば、ルールから外れているのでしょう。
「光る君へ」第5話「告白」で、道長(柄本佑さん)が、まひろに恋文をしたためる際に、当時は貴重な紙を使い、書き損じれば次々と新しい紙と取り替えていたのは、東三条邸(道長の父・兼家の邸宅)の豊かさを表しているように感じました。また、道長に恋文の代筆を申し出ていた行成(渡辺大知さん 小野道風、藤原佐理と並ぶ能書家 三蹟)の美しい文字で散らし書き(行の位置を定めず高低をつけ、墨の濃淡などで工夫を凝らす 行の上下を揃えて書くのは唐様)の文をもらって、さらにはお手本にしたいという女性も多かったようです。
常陸宮邸の女房たちが末摘花の部屋に入った光る君を咎めないのは、「世に類いなき」美しさだから。輝くほど美しいとされる光る君の具体的な容貌の特徴が、作中では曖昧なのは、美の基準は人によって違うので、心のなかでもっともイケメンだと感じる人物を思い描いて欲しいという紫式部の配慮のように感じます。「光る君へ」の放送開始直後は、藤原公任を演じる町田啓太さんの麗しさに、「彼こそ光る君」との呼び声も高かったもの。
実際の公任は「このあたりに若紫はおいでかな(≒若紫を描いたあなたも、きっとお美しいのでしょうね)」と紫式部に声をかけて「光る君みたいな方もいないのに、若紫がいるわけないでしょ」と聞き流されたことが「紫式部日記」に書かれています。なんだか「わたしの顔どう?」と自惚れる光る君と「見間違いでした」と応えた夕顔のようですね。
光る君の美しさについては曖昧なままにしている紫式部は、末摘花の容貌は容赦なく描写。光る君が鼻を赤く染めて若紫と戯れているのは、末摘花への明らかな揶揄いであり、いっそ清々しいほど。さらに「光る君へ」で道長の恋文に対して、まひろが行の上下を揃えた漢詩で応えるのは、光る君と末摘花とのやり取りが髣髴とします。
「紫式部日記」に弟よりも漢文を習得するのが早かったのに「一の字も書けない」ように振る舞っていたと記述されているのは、漢文が書ける女性が嫉妬の対象になる可能性があるということ。「末摘花って、あなたのことよね?」と同僚の女房たちに揶揄われつつ上手くやってゆけるように、紫式部は道化としての自分を末摘花に描き込んだのでしょうか。
光る君は、正妻の葵上のいる左大臣邸で、中務の君という女房とも関係を持っています。藤原公任が選んだ三十六歌仙の一人に、宇多天皇の親王・中務卿の子、女王(内親王の宣下のない皇族の女性)で歌人の中務(912-999年)という恋多き女性がいますので、「源氏物語」の中務の君も、末摘花と同じような血筋の女性かもしれません。第五帖「若紫」で光る君を手引きした藤壺の女房・王命婦も女王とされており、当時は「帝の血を引く」女性が女房として働くことも、まれではなかったようです。主人と男女関係にある女房のことを召人(めしうど)といい、中務の君はあまり良く思われていなかった様子が伺えますが、娘に寄り付かない婿を引き寄せるためにも、左大臣は優秀な女房を無碍にはできないのでしょう。
「光る君へ」で道長がまひろの看病をした際に「女の私には分かります。姫様と大納言様は間違いなく深い仲」と訴えたまひろの弟・ 惟規(のぶのり)の乳母・いとも、為時の召人のようにみえますが、家政を支え、まひろの就職や結婚に期待し、生活の逼迫を憂えるほどに一家にとって無くてはならない存在になっています。
光る君を末摘花に手引きした大輔の命婦も宮中で働いており、まひろも必要とあらば就活をする。「女房としては雇えませぬが、下女なら」と、まひろが就活の際に言われていたのは、主人に代わって歌を詠むなどの教養や当意即妙の才気を備えた女房として雇われたかったということになると思います。
末摘花は女房の侍従にフォローしてもらわなくてはならないほど、当意即妙からは程遠く、就活はままならなかったと思われることから、父宮亡きあと、後見してくれる人物を見つけるのは、本人にとっても、生活を共にする女房たちにとっても死活問題。光る君の言動は、すいぶんと身勝手にみえますけれど、手引きした命婦も、末摘花の女房たちも、生活を支えてくれることに関しては、おそらく期待どおり。愛の交歓には至らなくとも、末摘花が何とか生き抜いていけそうなことに、この時点ではホッとしていたのではないでしょうか。
まひろが就活に苦労していた意味や、「紙」が貴重品だったことなど、説明されなければわからない、わかればドラマが何倍も面白くなり、源氏物語への興味がわくこと満載!
特に末摘花の描写やその背景など、そんなところまで描いているのかと驚き、それを書いた紫式部への興味がさらに増しました。
次回もどうぞお楽しみに!!