「文春砲」には、実はかなり露骨な「タブー」が存在します。
これは噂でもなんでもなく、木俣正剛・元週刊文春編集長が、Diamond Onlineのコラムにて自ら次のように綴っています。
「文春砲」にタブーはないと誇らしげに言ってきましたが、実は、確実に書けない存在があります。それは作家です。
作家の作品への批評は、書評などに当然掲載されますが、人格批判やスキャンダルは一切書くことはしていません。作家にとって、文春は家族の一員のような存在であり、文春社員にとっては、メシのタネ。裏切るわけにはいかないというのがその大きな理由です。
(https://diamond.jp/articles/-/336336 より引用)
つい先日、愛人とのいざこざを暴露されていたベテラン声優氏も、作家だったら記事にされていなかったでしょうし、例えば同じ吉本興業所属の芸人でも、芥川賞をとった人であれば、松本人志のようなキャンセル・カルチャーの標的にはされなかったでしょう。
一方、上記の木俣元編集長がそうであるように、文春の内部的には「是々非々の大人の事情」的な正当化の意識が存在するようです。同じく元週刊文春編集長の花田紀凱も、文春への批判に対し「(出版社が)プラスマイナスを総合的に判断すれば(売れっ子作家の醜聞を)書かないのは当然」と発言したそうです(出典:https://iyakukeizai.com/beholder/article/2309)。
昨日の記事新谷学による「象徴天皇制」への言及で紹介した次の発言のように
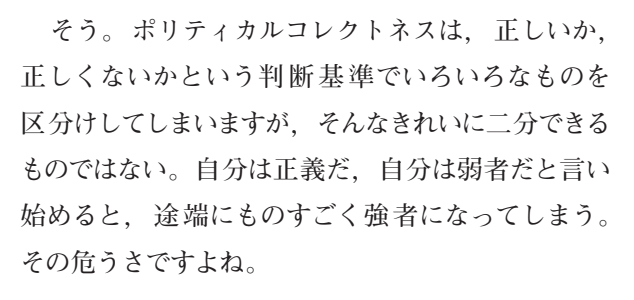
週刊文春は「文化を重視し護る者」的なスタンスを「ぶりっ子」する事が少なくありません。それは、「文壇」の中核を担う出版社という、一種のエリート意識に基づくものでしょう。
「文春砲の生みの親」と言われる、文藝春秋総局長(元・週刊文春編集長)・新谷学などはそうした部分での振る舞いが実に「巧く」、先述の記事で参照したインタビューでは次のような発言もしています。
まっとうな保守とは本来そんなに過激なものではない。もっと穏やかで,さっき申し上げたサイレントマジョリティーをしっかりとすくい上げていくものが保守だと思いますが,なにか非常に攻撃的な,排他的なものが保守だとなっているので,まともな保守論壇をもう1回ちゃんと創れるといいなと思っていますけどね。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2022_03/p16-19.pdf より引用
これは一見すると、「Hanada」などギトギトのエセ保守系メディアに嫌悪感を持つ層にも好意的に受け止められる、バランスのとれた発言のようにも見えます。
しかし、実際には「言っているようで、何も言っていない」。新谷の著書「獲る・守る・稼ぐ 週刊文春『危機突破』リーダー論」などを読むと非常によくわかるのですが、この人物はポリコレやコンプラといった「面倒事」の隙間やツボの見極めが巧く、それらを「安全な場所から」利用する事に長けています。その意味で、非常に「優秀」な編集者と言えるでしょう。
しかし、実際の文春の取材姿勢などを見ると「???」となるように、それは実際の思想とはリンクしていない「外面」です。
わかりやすく、同時に深刻な例で見てみましょう。
特に日本において、キャンセル・カルチャーの蔓延で危惧される最も深刻な展開は「天皇・皇室のキャンセル」につながる事です。
それを念頭に、同インタビュー中の天皇制に関する箇所を再度読んでみます。
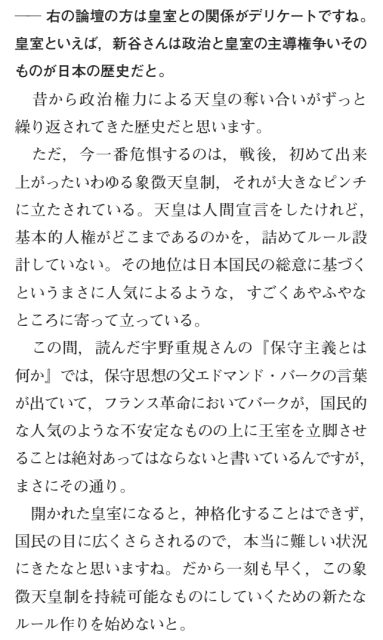
前回のブログでも書いたように、エドマンド・バークの引用で「保守的な憂慮のフリ」をしているものの、文春は皇室バッシングの記事を数多く載せていると同時に、「基本的人権」を起点としたルール作りといった観点を中心にすると、「天皇・皇室を廃止した方が良い」という結論に言ってしまう危険度が高い。
この発言は、皇室を重視するような素振りを見せながら、ある種頑迷な男系固執者などよりずっと深い「皇室存続への危険」を含んでいます。
文春の記事は「感情を排したルールや合理性を装って、人々の嫉妬心や俗な好奇心を正当化する」ものですが、天皇・皇室を戴くというのはその真逆で「国民の熱望によって立場をお引き受けいただき、その関係性の先に、国柄に立脚した秩序や合理性が生まれる」というものです。
「文春に感じる違和感・危険さ」は、単なるスキャンダリズムの嫌悪ではなく、日本の国柄・文化の根幹部分を毀損する性質への危惧だというのが、現在の私が内的に至っている結論です。
これを念頭に、本日14:00からのゴー宣DOJO in大阪「週刊文春を糾弾せよ!」に臨みます。今回は全編ネット配信されるので、会場に来られなかった方もそれぞれの形でぜひ「参加」してください!





















