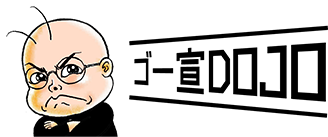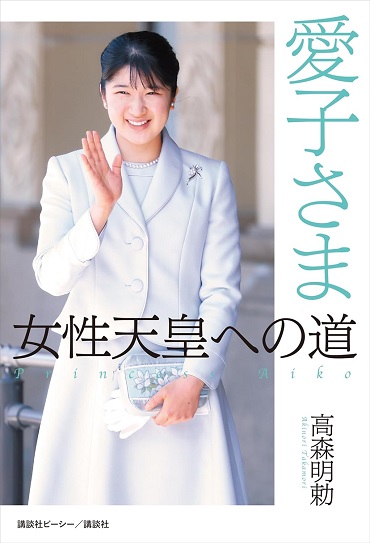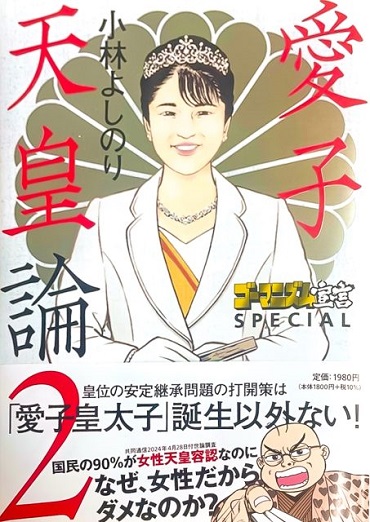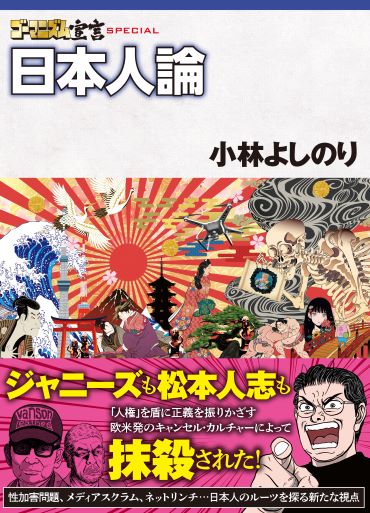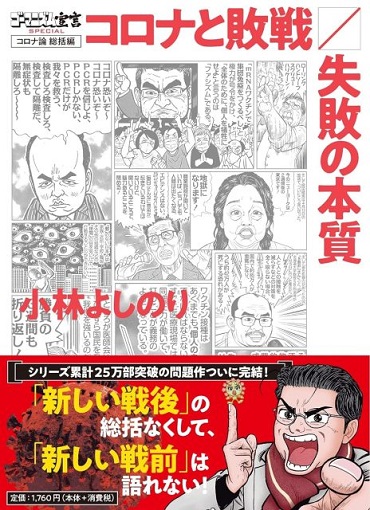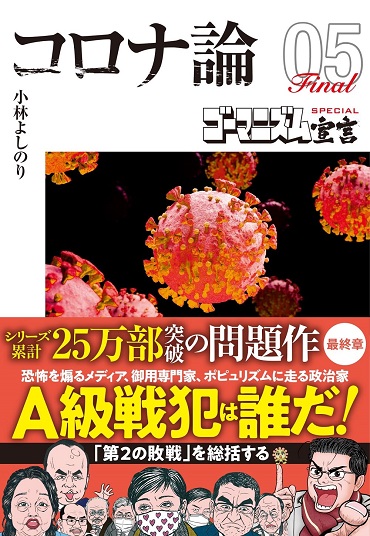「光る君へ」と読む「源氏物語」第4回 第四帖<夕顔 ゆうがお> byまいこ
「早く皇子を産め!」「光る君へ」で藤原道隆(井浦新さん)や伊周(三浦翔平さん)が定子(高畑充希さん)に向かって迫った言葉は、多くの視聴者を震撼させました。また、詮子(吉田羊さん)と定子との確執も鮮明になってきました。
平安時代の天皇の妃の序列は、正妻である中宮(ちゅうぐう)もしくは皇后、次に女御(にょうご 父の地位が大臣以上)、最期に更衣(こうい 大納言以下 光る君の母も更衣)となり、皇子・皇女を産んだ女御・更衣のことを御息所(みやすどころ)という場合もあります。
中宮は、もともと皇后、皇太后、太皇太后の三后を表す言葉で、一条天皇の時代には三つの座が埋まっていたにも関わらず、道隆はゴリ押しで、皇后を「中宮」と「皇后」に分け、娘・定子を中宮にしました。詮子は円融天皇の皇子を産んでも皇后になれず、一条天皇が即位したことで、ようやく皇太后になれたのに対し、定子は皇子を産まないうちに中宮になったことも、確執の原因の一つかもしれません。
「源氏物語」で光る君を目の仇にする弘徽殿女御が、詮子がモデルになっていると言われるのは、皇子を産んだにも関わらず円融天皇の寵愛も皇后の座も、後から入内した妃に奪われる三角関係に陥ったことなどから。
三角関係は、「光る君へ」の主人公二人にもみられます。まひろを想うのは、道長、直秀、道綱、そして宣孝も。道長は、倫子、明子を妻としつつ、想いはまひろに。
第三帖で取り上げた平安時代の寝殿造、「寝殿の東・西・北側に建つ妻子や一族が住む対屋(たいのや)」には、それぞれ別の妻を迎えることが可能で、当時はリアル「3人同棲」も多かったことでしょう。
現代は、リアルは難しいものの、三角関係は健在で、胸の内には苛烈な「心の鬼」を飼い、魂が抜け出るまで追い詰められてしまうこともあるのでは?今回は、「源氏物語」屈指の魅力ある女性への嫉妬によって、誇り高き女性が生きながらに「思念を凝固」させてしまったかもしれない、そんな様子も見てみましょう。
第四帖 <夕顔 ゆうがお (夕方に咲き翌朝はしおれる白い花 儚い恋)>
光る君は、身分高く美しい六条御息所(ろくじょうのみやすどころ かつて東宮妃で皇女を産むも東宮が亡くなり宮中を出て六条に住んでいる)のもとに通う途中で、従者の惟光(これみつ)の母(光る君の乳母 惟光は光る君の乳兄弟)の病気見舞いをすることにしました。猥雑な五条の通りで門が開くのを待つ間に、隣の家に咲く白い花が目に入ったので所望すると、花をのせた扇に歌が書いてあります。
心あてに それかとぞ見る白露の ひかりそへたる 夕顔の花 夕顔
もしかしたら光る君かしら 白露でさらに輝く美しき 夕顔のようなそのお顔
心ひかれた光る君は、歌を詠みかけた女主・夕顔のもとに通い始めました。女房たちの噂によると、どうやら夕顔は「雨夜の品定め」で頭中将(葵上の兄 とうのちゅうじょう 位階は四位 天皇の傍に仕える蔵人所のトップ・蔵人頭(くろうどのとう)と近衛中将を兼ねるエリート)が告白した恋人のようです。可愛らしく、頼りなげながら、恋のことわりも知らぬわけではない夕顔の魅力に溺れた光る君は、六条には足が向かなくなってしまいます。
五条の家で朝を迎えると、人々の声や米を搗いたり布を打ったり(艶を出すため)と近隣の生活音がさまざまに聴こえてくるのを面白く感じつつ、もっと落ち着いて過ごしたくなった光る君は、「なにがしの院」という邸に夕顔を連れ出しました。
邸はひどく荒れはてて、門の上には草が茂り、庭には人気がなく、老木が鬱蒼として、池も水草に埋もれています。「ずいぶん気味が悪いところだけれど、鬼がいてもわたしのことは見逃してくれるだろうね」といい、身分を隠すために付けていた覆面を取った光る君は「わたしの顔、どう?」と夕顔にたずねました。
光ありと見し 夕顔の上露は たそかれどきの そら目なりけり 夕顔
露で光る夕顔のようにあなたが美しくみえたのは、黄昏時の見間違いでした
歌を面白く感じて、光る君は夕顔をさらに愛しんで過ごしつつ、六条御息所も、もう少し打ち解けてくれたらとつい比べてしまいます。夜になり、光る君が夕顔とまどろんでいると、凄絶に美しい女の物の怪が現れました。「こんな女に心奪われて」と手をかけられた夕顔は息が絶えてしまいます。泣く泣く光る君は、惟光に弔いを任せ、いったんは二条の自邸に戻りますが、諦めきれずに鳥辺野を望む清水寺の近くまで夕顔に会いにゆきました。
亡骸の手を取って嘆き悲しみ、帰路には落馬するほど心乱れ、寝込んでしまった光る君に、「なにがしの院」にもついてきていた女房の右近は、夕顔が三位中将(三位の近衛中将 近衛中将の位階は通常は四位 家柄が良いと三位になる場合がある)の娘で、頭中将の正妻に脅されて乳母の元に身を寄せており、小さな娘もいると伝えます。光る君は娘を引き取ろうとしますが、方違えで使っていただけの五条の家には、すでに誰もいなくなっていました。
その頃、空蝉の夫・伊予介が任地から戻り、主筋にあたる光る君に「娘(軒端荻)は結婚させ妻は伊予に連れてゆく」と伝えます。源氏は伊予へ向う空蝉に、たくさんの贈り物と共に、あの持ち帰った衣を返したのでした。
***
「光る君へ」でまひろが恋文の代筆の仕事に向かう際や、大道芸である散楽が披露される場面での町の猥雑さは、「夕顔」の帖で描かれた五条あたりの市井の人々の様子が髣髴といたしました。さらに散楽の直秀が藤原氏批判の劇で顔を隠していた布が落ちたシーンは、光る君の顔を隠していた覆面とは、こういったものかと感じ入りました。
夕顔の詠んだ二つの歌の「ひかり」「光(ひかり)」は、古語で「光る、輝く、(容姿などが)美しく輝く」、「光る君」は「光り輝くような美しい御方」。現代でも突出した才能や美しさや品格を持つ人に輝くばかりのオーラ、魅力を感じ、「光っている」という表現をする場合がありますね。
夕顔は「源氏物語」の人気キャラクター。光る君が素顔を見せ「わたしの顔、どう?」ときいた際には歌で意外な応えをする。誘えば何処までもついてくる、儚げな白い花のように見えて、自惚れにはさらりと抗う意外性も、魅力なのでしょう。
そもそも二人が逢瀬を重ねるきっかけも、女性の方から。夕顔を遊女に例える向きもあるようで、遊郭の格子窓から道行く人に手を伸べ声をかけるように、白い花の絡む粗末な家からの歌の詠みかけは、花をのせる移り香のしみた扇にしたためて、男性を興ざめさせないほどの絶妙な積極性。さらに荒れ果てた邸での逢瀬や、子供が生まれたばかりという想いの高まる頂点で去ってしまうことで、光る君にも頭中将にも、夕顔は忘れ得ぬ人になりました。
「なにがしの院」は、「宇治拾遺物語」に「河原院融公の霊住む事」として、はっきりと物の怪として描かれた源融(みなもとのとおる)の邸「六条河原院」とされています。当時の人は、「六条」「なにがしの院」と聞いただけで、「え?もしかして河原院?光る君、そんなところに女性を連れて行って大丈夫?」と思いながらスリルを楽しんでいたかもしれません。
夕顔に手をかけた物の怪は、誰だったのか。「夕顔」の帖で特定はされていないものの、光る君が二人の女性を心の中で比べると、すぐに物の怪が現れたことから、六条御息所と解釈する場合もあるようです。
「光る君へ」で源明子を演じる滝内公美さんは制作者の方から「役柄のヒントは源氏物語でいう“六条御息所”」と言われたとのこと。花山天皇を騙して退位させ、藤原兼家が摂政に上り詰めた寛和の変(986年)の以前に、安和の変(969年)で明子の父・源高明(みなもとのたかあきら)は藤原氏の策謀で謀反の容疑ありとして失脚させられています。明子が道長の妻となり、兼家の扇を手に入れて呪詛する姿は、生きながらに「思念を凝固」させる様が映像化されたようにもみえました。
「なにがしの院」での逢瀬と、鳥辺野を望む場所での哀悼も、「光る君へ」に反映されているように思います。散楽の直秀たちを鳥辺野で埋葬するクライシスを共にしたまひろと、荒れ果てた邸で結ばれた道長は、生きる志を世の中を変える方に向けてゆく。過ちを繰り返しながら、だんだんとオーラを増し、為政者としての実力をつけてゆく有り様を、柄本佑さんは見事に演じてゆかれるのではないでしょうか。
ケガレなど物ともせず、愛した女性が亡骸となっても会いに行き、悲しみのあまり落馬までしてしまう。読者と物語が恋に落ちる劇的な瞬間。いろいろとやらかす光る君にも、本当の意味での、ひかりそへたる、さらに輝くオーラをそえるのは、夕顔を恋う涙だったかもしれません。
ところで、空蝉を任地に伴うことにした伊予介は、光る君と妻の関係に気づいたのでしょうか?コキュ、または寝取られ問題は「源氏物語」に度々登場しており、あれこれと1000年経っても読者に考察させる紫式部です。
【源氏物語ゆかりの地めぐり・渉成園&六道の辻】
「なにがしの院」とされる「六条河原院」は、京都駅から歩いてゆける美しい庭園「渉成園」もその一部。「鳥辺野」は、清水寺の南方の阿弥陀ヶ峯あたり。清水寺の西方には鳥辺野の入口「六道の辻」があり、冥界と俗界が隣り合わせであることが感じられます。
「光る君へ」と読む「源氏物語」
第1回 第一帖<桐壺 きりつぼ>
第2回 第二帖<帚木 ははきぎ>
第3回 第三帖<空蝉 うつせみ>
コンプライアンスだの人権だのという近代西洋の薄っぺらいイデオロギーを持ち出して、どうのこうの言っている人には死んでもわからない、1000年前から今も通じる日本人の物語、次回もどうぞお楽しみに!