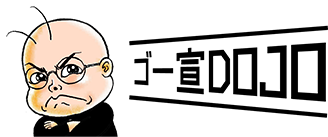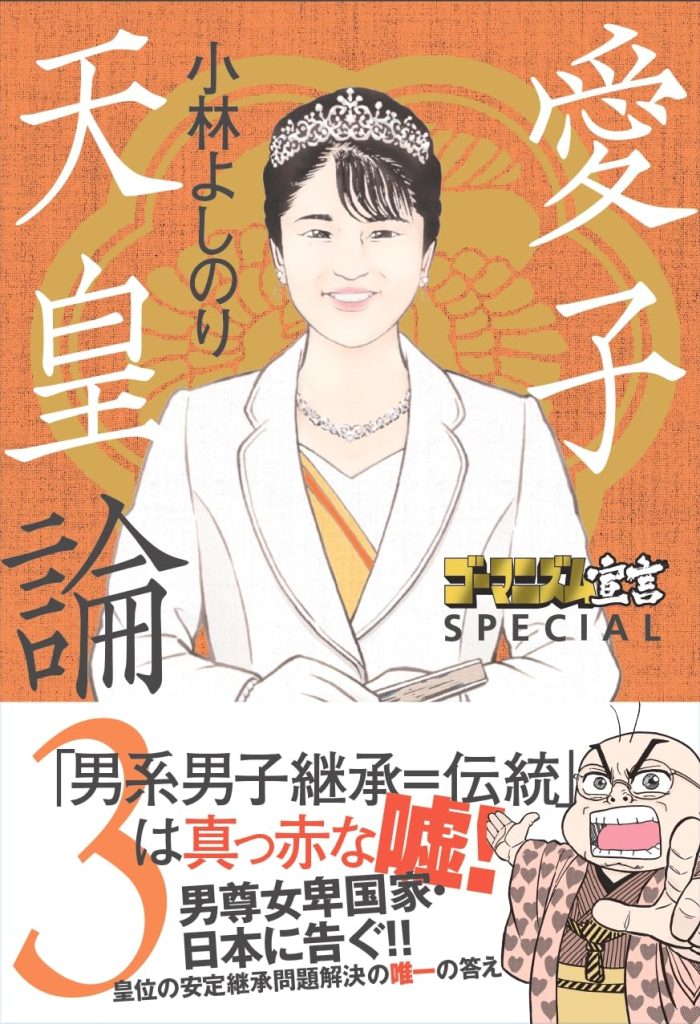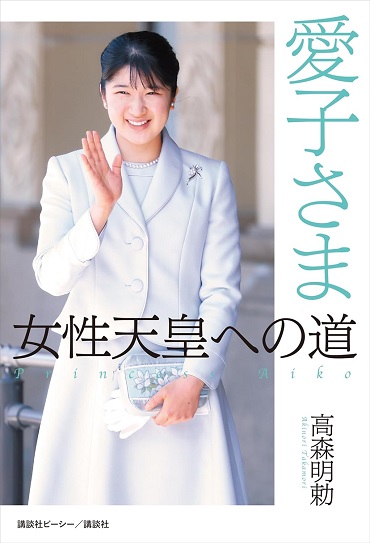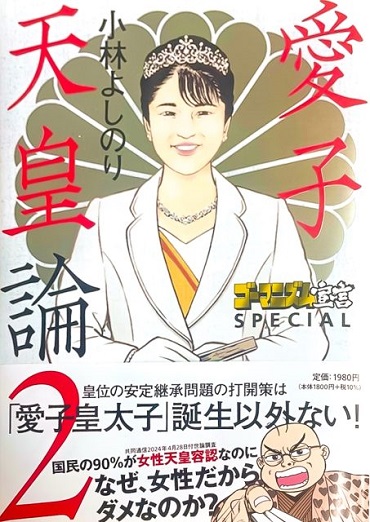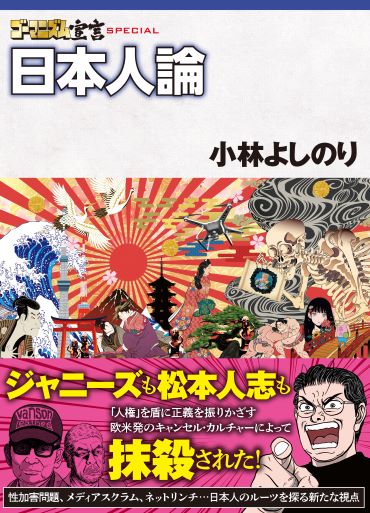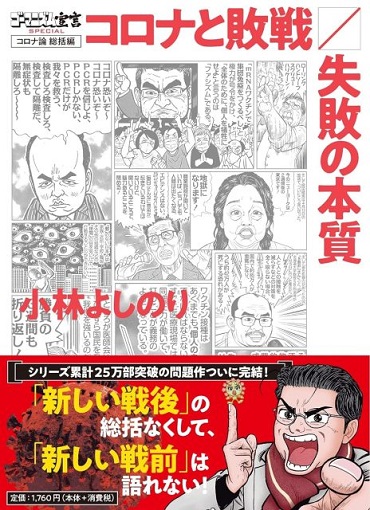~光る君へ~
愛子さま立太子への祈念と読む「源氏物語」
第33回 第三十三帖<藤裏葉(ふじのうらば)>byまいこ
「光る君へ」第40回の冒頭は、一条天皇と彰子が仲睦まじく並ぶ藤壺で、女房が第三十三帖「藤裏葉(ふじのうらば)」を読み上げていました。「源氏の物語」を愛好した一条天皇は藤壺に足を運ぶようになり、彰子は入内して9年経ってようやく「愛を知る」ことになり、二人の皇子が誕生。道長の一族が天皇の外戚になる近い未来の繁栄を予感させる雰囲気の中で、「源氏物語」第一部のラストが読まれるという描写に感じ入りました。
今回は、長年、「愛を知りたい」と願っていた者たちが、大団円を迎えるさまをみてみましょう。
第三十三帖 <藤裏葉 ふじのうらば(藤の花の裏葉(葉末 葉の先) 内大臣が口ずさんだ古歌より)>
明石の姫の入内の準備で忙しいなかでも、夕霧の宰相(さいしょう 太政官の官職・参議の唐名)の中将は物思いに沈みがちで、こんなに雲居の雁が恋しいなら、内大臣も弱気になっているという噂もあるので「同じことなら外聞が悪くならないよう最後まで自分を貫こう」と念じつつ、思い悩んでいます。雲居の雁も、内大臣から夕霧の縁談の噂を聞いて嘆かわしく、二人は互いに背を向け合いながらも相思相愛なのでした。
強気だった内大臣も「中務の宮が夕霧を婿と決めたら、改めて雲居の雁の婿選びをするのは相手にも気の毒で、私も世間に笑われてしまうだろう。何とか取り繕って、やはりこちらが譲らねばなるまい」と思います。
三月二十日(新暦で四月末頃)は亡き大宮(内大臣の母 夕霧と雲居の雁の祖母)の命日で、内大臣は法事で極楽寺に詣でます。内大臣の息子や上達部も数多集まるなか、夕霧は誰にも劣らぬ美々しい装いに容貌も今を盛りの成熟ぶりで、何もかも見事な様子です。
夕方になって皆が帰る頃、花が散り乱れ、霞が立ちこめる風景を眺めた内大臣が物思いに耽っていると、夕霧も同じ風景にしんみりとして「雨になりそうだ」と人々が騒ぐのも気にとめず、思い沈んでいます。内大臣は心ときめくものを感じたのか、夕霧の袖を引いて「なぜ、そんなに私を責めるのです。今日の法事は大宮のためと思って、その縁に免じて許して下さい」などと言いました。
「亡き大宮も、あなたを頼りにするようにとの御意向と聞いておりましたが、許していただけない御様子でしたので遠慮しておりました」と夕霧が応えたところ、急な雨風となり、皆は散り散りに帰ります。夕霧は「どういうおつもりで、いつになく親し気にされたのだろう」と内大臣の言葉が耳に残り、あれこれ考えて夜を明かしました。
四月初め(新暦で五月初旬)頃、藤の花が咲き乱れる盛りに、内大臣の邸で管弦の遊びが催されることになり、内大臣は息子の柏木を使者として夕霧を招待する文を遣わします。
わが宿の藤の色濃きたそかれに 尋ねやは来ぬ春の名残を 内大臣
わが家の藤の花(雲居の雁)の色濃い黄昏に 訪ねて下さいませんか 春の名残を求めて
なかなかに折りやまどはむ藤の花 たそかれ時のたどたどしくは 夕霧
かえって折ってよいものか惑うことでしょう 黄昏時に藤の花が仄かに浮かぶ頃では
夕霧から内大臣の文を見せられた光る君は「わざわざ使者を寄越されたのだから早く出かけなさい」と言い、自分の衣の中でも格別に素晴らしいものを夕霧に遣わしました。
夕霧は念入りに身なりを整えて、黄昏時も過ぎ、先方が気を揉む頃に出かけます。月が昇っても、まだ藤の花の色がはっきりと見えないほどの暗さでしたが、花見にことよせて盃が巡り、管弦の遊びなどをするなか、内大臣は酔ったふりをして夕霧に盃を勧め、古歌を口ずさみます。
春日さす藤の裏葉のうらとけて 君し思はば我も頼まむ 「後撰集」読み人知らず より
春の日がさす藤の裏葉(葉末 葉の先 子孫)のうら(心、内心)ではないけれど、あなたの心がうちとけて、娘を思ってくれるなら、私もあなたを信頼しましょう
次第に夜も更けて、夕霧は酔ったふりをして「お酒をいただいて家まで帰れそうにありません。泊まる所を貸してもらえませんか」と柏木に頼むと、内大臣は「お泊りになる所に案内しなさい。年寄りは酔い過ぎて無礼なので退出しましょう」と言い捨てて、引き下がりました。
柏木は心の内に「しゃくだな」と思いつつ、夕霧の人柄が素晴らしく「こんな結果になって欲しい」と期待していたので、安心して妹の雲居の雁の寝所に案内します。夕霧は夢かと思いながら自分を誇らしく感じていることでしょう。雲居の雁は恥じらいつつも、以前より成熟して、得も言われぬ美しさなのでした。
ことの次第を聞いた光る君は、いつもよりも光り輝くように美しい夕霧が六条院に参上したのを見て「賢い人でも女性のことでは心乱れるものなのに、焦らずに過ごしてきたのは、少しは人より優れた心構えだったね。それでも得意になって浮気心など見せないように」などと教えます。光る君は夕霧の父親というよりも、少し年上の兄のようで、二人が別々にいると同じ顔を写し取ったように見えるのですが、一緒にいるとそれぞれに特色があって素晴らしいのでした。
明石の姫の入内は、四月二十日(新暦で五月末)過ぎと決まります。その年の賀茂の祭りの勅使(ちょくし 帝の使者)の行列を、光る君は紫の上と見物に行きました。光る君は夕霧の母・葵上と秋好中宮の母・六条御息所の車争いを思い出し「後に残った子孫として、夕霧は並の臣下として少しずつ出世してゆくでしょう。秋好中宮は並びなき地位に昇られたのは感慨深いものです。なべて無常な世だからこそ、何ごとも生きている限り自分の好きなように過ごしたいものの、私の死後、残されたあなたが落ちぶれてしまわないかと気がかりで」などと紫の上に語ります。
惟光の娘の藤典侍(とうのないしのすけ)も勅使で、夕霧は文を届けます。二人は人目を忍んで思いを交わしている仲なので、夕霧が内大臣の婿になって藤典侍は心穏やかではありませんが、夕霧の心は離れず、これからも人目を忍んで逢うことになるでしょう。
入内には正妻が付き添うのが慣例でしたが、光る君は「紫の上は長く明石の姫の側に付いてはいられないので、この機会に実母の明石の君を後見にしよう」と思います。紫の上も「こんなに離れて暮しているのを明石の君は嘆いているだろうし、明石の姫も内心では母君が慕わしく、寂しく思っているだろう」などと思い、光る君に「この機会に明石の君を付き添いにして上げて下さい」と言いました。光る君から紫の上の言葉を伝えられた明石の君は、たいそう嬉しく、女房の衣装や、その他のことも紫の上に劣らないように準備します。明石の尼君は孫娘の生い先を見たいと願い、入内後はどうしたら逢えるだろうかと悲しくなるのでした。
入内の儀式を「耳目を驚かせるようなことはしない」と光る君は控えめにしましたが、自然と世間並にはおさまりません。入内の日の夜に付き添った紫の上は、宮中で三日過ごしてから退出する際に、入れ替わりに参内した明石の君と初めて対面します。
「明石の姫が成長して長い年月が経ったと思えば、もう他人行儀な隔てはお互いに残りませんわね」と、紫の上は親しげに話しつつ、明石の君が物を言う気配などに「光る君に愛されるのも無理もない」と思います。明石の君も、気高く今を盛りに美しい紫の上を「光る君に愛されて並ぶ者もない立場にいるのも、もっともなこと」「この紫の上と対等に話せる自分の運勢も疎かなものではないわ」と感じています。明石の君が大切に世話をする上に、聡明で並外れて美しい明石の姫を、東宮も格別と思うのでした。
来年は四十歳になる光る君のお祝いを、朝廷をはじめ世をあげて準備しています。この秋に、光る君は准太上天皇の位(じゅんだいじょうてんのう 太上天皇に准じた位 実際にはない)を得ましたが、冷泉帝は父の光る君に譲位できないのを嘆いています。
内大臣は太政大臣(国政の最高機関である太政官の最高の官。国政を総裁し、左右大臣の上に位置し適任者がいない時は欠員 位階は正一位か従一位)となり、夕霧は中納言(太政官の次官 位階は従三位)になりました。夕霧が「いくら立派な人でも六位なんかではね」と侮った雲居の雁の乳母に「あの辛かった時の一言が忘れられないな」と言いながら艶やかに微笑むと、乳母は「どんなにお気に障ったことでしょう」と応えます。夕霧は亡き大宮の三条の邸を美しく改装して、雲居の雁と移り住みました。
十月二十日過ぎ(新暦で十一月二十日頃)に、六条院に帝の行幸がありました。紅葉の盛りの趣き深い行幸で、朱雀院も赴くことになり、六条院では心を尽くして、まばゆいほど立派な準備をしました。帝と朱雀院の御座が二つ設けられ、光る君の御座は一段下にあったのを、宣旨(せんじ 天皇の御意向を下達すること)によって同列に直したのは素晴らしいことでしたが、帝は充分に礼を尽くせないと残念に思います。
日が暮れかかる頃、宮中の楽人が演奏し、殿上童が舞うと、その昔の紅葉賀が思い出されます。太政大臣の末の十歳の息子が上手に舞って、帝が衣を脱いで褒美にすると、太政大臣は庭に下りて拝舞しました。光る君は青海波を舞ったことを思い、太政大臣も「あの時は光る君と同じ青海波を舞い、人よりも高い身分になったけれど、やはりこの方には到底及ばなかった」と悟ります。
帝の容貌はますます整って、光る君と瓜二つのようです。側に控える夕霧も帝にそっくりで、気品の高さでは劣るものの、艶やかさは優っているように見えます。夕霧が笛を吹き、弁の少将が歌い、やはり優れた人が揃う両家なのでした。
***
12歳の夕霧と14歳の雲居の雁の仲を引き裂いてから6年、とうとう内大臣は自ら白旗をあげました。娘を藤の花に見立てて誘うあたり、「べらぼう」第三回で蔦重が「一目千本 華すまひ」という本を作り、遊女を花に見立てて描かせ、人々を吉原に誘ったさまにも通じるようで、まことに艶ではありませんか。
第一帖「桐壺」で光る君は12歳で元服後、すぐに葵上と結婚しますが、打ち解けられず、第二帖「帚木」で17歳になった時は、幾人かの女性と関係をもっていました。「桐壺」と「帚木」の間に、「輝く日の宮」という失われた帖があったという説があり、藤壺、六条御息所、朝顔の君、筑紫の五節などの女性との馴れ初めが描かれていたとされています。
光る君は元服から5年の間に、不義の子を産んだ藤壺、物の怪となった六条御息所などと、恋にうつつを抜かした挙句、朧月夜を帝から奪い、須磨に隠遁した自分の轍を踏まぬように、元服した12歳の夕霧を六位という低い身分にして、大学寮に入れて学ばせたのでしょう。
光る君の深慮と夕霧の努力が報われて、内大臣と夕霧は和解、両家は再び結ばれました。明石の姫も入内し、紫の上と明石の君も手を結び合ったようにみえます。
光る君が准太上天皇という立場になったのは興味深いですね。「光る君へ」第44回、三条天皇(木村達成さん)の第一皇子・敦明親王(阿佐辰美さん)は東宮に立てられたものの、三条天皇の死後、後見を失い、自ら東宮の地位を下りていました。その見返りとして、敦明親王は「小一条院」の院号(上皇に対する尊称)を賜り、太上天皇に准じる待遇になります。これが皇位につかずに院号を賜った最初の例とのことで、光る君が「准太上天皇の位」を得たという創作部分に活かされているのかもしれません。
これで「源氏物語」第一部が完結いたしました。大団円を迎えたのも束の間、第二部からは、まひろが「藤裏葉」を書き上げた後、「罪 罰」と記したことが光る君に起き、「夫婦の絆」が大きく揺らぎます。どうぞ続きも御覧いただけましたら幸いです。
【バックナンバー】
第1回 第一帖<桐壺 きりつぼ>
第2回 第二帖<帚木 ははきぎ>
第3回 第三帖<空蝉 うつせみ>
第4回 第四帖<夕顔 ゆうがお>
第5回 第五帖<若紫 わかむらさき>
第6回 第六帖<末摘花 すえつむはな>
第7回 第七帖<紅葉賀 もみじのが>
第8回 第八帖<花宴 はなのえん>
第9回 第九帖<葵 あおい>
第10回 第十帖 < 賢木 さかき >
第11回 第十一帖<花散里 はなちるさと>
第12回 第十二帖<須磨 すま>
第13回 第十三帖<明石 あかし>
第14回 第十四帖<澪標 みおつくし>
第15回 第十五帖<蓬生・よもぎう>
第16回 第十六帖<関屋 せきや>
第17回 第十七帖<絵合 えあわせ>
第18回 第十八帖<松風 まつかぜ>
第19回 第十九帖<薄雲 うすぐも>
第20回 第二十帖<朝顔 あさがお>
第21回 第二十一帖<乙女 おとめ>
第22回 第二十二帖<玉鬘 たまかずら>
第23回 第二十三帖<初音 はつね>
第24回 第二十四帖<胡蝶 こちょう>
第25回 第二十五帖<蛍 ほたる>
第26回 第二十六帖<常夏 とこなつ>
第27回 第二十七帖<篝火 かがりび>
第28回 第二十八帖 <野分 のわき>
第29回 第二十九帖 <行幸 みゆき>
第30回 第三十帖 <藤袴 ふじばかま>
第31回 第三十一帖<真木柱(まきばしら)
第32回 第三十二帖<梅枝(うめがえ)>
ここまで光源氏を中心に、本当に様々な愛も怨みも絡みあってきた物語が、円満にひとつの終着点を迎えたことに、しみじみと感慨深い気持ちになりました。
…と思ったら、これもつかの間、次にはさらなる波乱が待ち構えているとのこと、全然目が離せません!
次回もどうぞお楽しみに!!